便に血が混じると、誰しも不安に感じるものです。真っ赤な鮮血や黒っぽいタール状の便など、出血の状態によって疑われる病気や原因はさまざまです。
痔や裂肛などの良性疾患が原因となる場合が多いですが、なかには大腸がんや炎症性腸疾患など重篤な病気が隠れていることもあります。
この記事では、便に血が混じる原因について詳しく解説します。血便や下血が起きたときの受診目安や、病院での検査方法もまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

便に血が混じると、誰しも不安に感じるものです。真っ赤な鮮血や黒っぽいタール状の便など、出血の状態によって疑われる病気や原因はさまざまです。
痔や裂肛などの良性疾患が原因となる場合が多いですが、なかには大腸がんや炎症性腸疾患など重篤な病気が隠れていることもあります。
この記事では、便に血が混じる原因について詳しく解説します。血便や下血が起きたときの受診目安や、病院での検査方法もまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
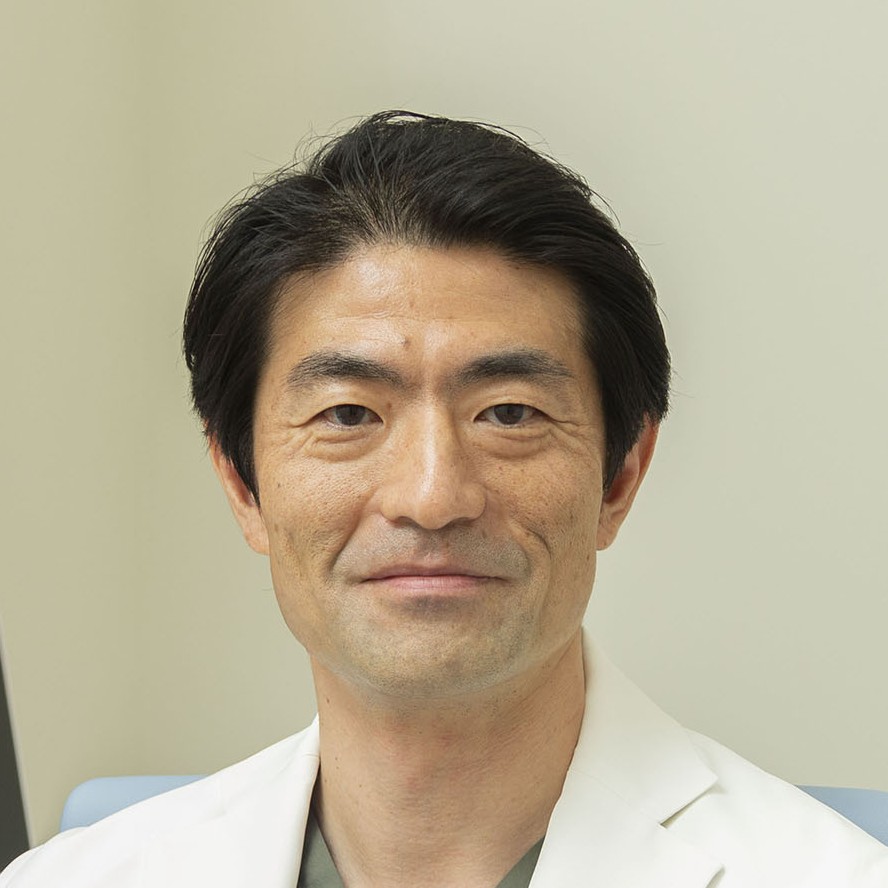

ここでは、血便や下血の種類について解説します。血便の種類ごとに「便の状態」「疑われる出血部位」「主な原因疾患」「検査方法」を整理しました。
| 血便・下血の種類 | 便の状態 | 疑われる出血部位 | 主な原因疾患 | 検査方法 |
|---|---|---|---|---|
| 黒色便 | タール状で黒くドロッとしている | 胃・十二指腸(上部消化管) | 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん | 胃カメラ検査、血液検査 |
| 暗赤色便 | 暗い赤褐色でややドロッとしている | 小腸~大腸 | 感染性腸炎、虚血性腸炎、大腸憩室炎、大腸がん | 大腸カメラ検査、腹部エコー、腹部CT検査 |
| 粘血便 | ゼリー状の粘液に血が混じる(イチゴジャム状) | 大腸 | 潰瘍性大腸炎、クローン病、大腸ポリープ、大腸がん、赤痢 | 大腸カメラ検査、血液検査、腹部CT検査 |
| 鮮血便 | 鮮やかな赤い血が便の表面やトイレットペーパーに付着 | 直腸・肛門 | 痔核(いぼ痔)、裂肛(切れ痔)、直腸ポリープ、直腸がん | 肛門鏡、直腸診、大腸カメラ検査 |
なお、それぞれの便の種類によって、他の症状を併発している場合があります。
みぞおちの痛み、貧血、吐き気など
腹痛、下痢、発熱など
腹痛、発熱、下痢など
排便時の痛み、出血のみで他の症状がないことも多い
血便は出血部位や疾患によって見た目が異なるため、正確な判断には医師の診察が不可欠です。気になる症状がある場合は、早めの受診を検討してください。

便に血が混じる原因となる病気として、以下が挙げられます。
ここでは上記の病気についてそれぞれ解説します。
痔核(いぼ痔)は、肛門の周囲の血管がうっ血して腫れることで発生する良性疾患です。
便秘や長時間の座り仕事、強いいきみなどが主な原因とされます。
排便時に鮮やかな赤い血が便に付着したり、トイレットペーパーに血が付いたりすることが多く、痛みが伴うこともあります。
内痔核は無痛性で出血のみが症状となることもあり、気づきにくい場合があるため注意が必要です。
再発しやすいため、生活習慣の見直しや場合によっては外科的治療が必要になります。
裂肛(切れ痔)は、肛門の皮膚が排便時に切れて出血や痛みを引き起こす病気です。
特に硬い便や排便時のいきみによって肛門が傷つくことで発生することが多いです。
出血は鮮血であることが多く、トイレットペーパーに血が付いたり、便器が赤く染まるほど血が出るケースもあります。
排便時の激しい痛みが特徴で、排便を避けて便秘が悪化するという悪循環に陥ることもあります。
慢性化すると肛門ポリープ、見張りイボや潰瘍を形成することもあるため、早めの対処が大切です。
大腸がんは、初期段階では自覚症状がほとんどありませんが、進行すると便に血が混じる症状が現れます。
がん組織はもろく、便との摩擦で出血しやすくなるためです。
出血の色は暗赤色や黒色になることが多く、他にも下痢や便秘、便が細くなるといった症状がみられる場合もあります。
日本では罹患数の多いがんであり、早期発見・早期治療が生存率に直結します。
血便が見られた際は、迷わず病院で大腸カメラ検査を受けることが大切です。
大腸ポリープは大腸の粘膜にできる隆起性の病変で、良性であっても出血の原因になることがある病気です。
便がポリープに接触することで出血を引き起こすケースが多く、無症状でも偶然見つかることもあります。
なかには将来的にがん化する『腺腫性ポリープ』も存在し、早期に発見して切除することで大腸がんの予防につなげられます。
大腸カメラ検査によって診断と同時に日帰りで切除することもできるため、検査を受けてみましょう。
潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に炎症や潰瘍を起こす原因不明の疾患で、炎症性腸疾患のひとつです。
活動期と寛解期を繰り返すのが特徴で、活動期には下痢や血便、腹痛、発熱などを伴います。
粘血便がみられ、重症化すると日常生活に支障をきたすこともあるため注意が必要です。
現在の医学では根治が難しく、症状を抑える薬物治療や食事管理によって寛解期を長く保つことが目標となります。
大腸がんのリスクに加えて、胃にも同時性の病変を認めることもあるため、定期的な大腸カメラや胃カメラ検査が必要です。
クローン病は、口から肛門までの消化管のどこにでも炎症を起こす可能性がある難病で、特に小腸と大腸に発生することが多いです。
腹痛や下痢、発熱、体重減少といった症状のほか、活動期には血便が見られることがあります。
潰瘍性大腸炎と同じく炎症性腸疾患の一種で、再発と寛解を繰り返すのが特徴です。
原因は明確にはわかっていませんが、免疫異常や遺伝的要因、腸内細菌との関係が指摘されています。
放置すると他の合併症を引き起こすため、継続的な治療と定期的な大腸カメラ検査や胃カメラ検査が重要です。
感染性腸炎は細菌やウイルス、寄生虫が腸に感染することで発症する炎症性の疾患です。
原因となる病原体には、カンピロバクター、サルモネラ、腸管出血性大腸菌(O157など)などがあります。
症状としては血便のほか、激しい腹痛、発熱、下痢、嘔吐などがみられ、特に腸管出血性大腸菌によるものでは重症化することもあります。
不衛生な食品や水、海外渡航などが関係することが多く、予防と早期診断が重要です。
大腸憩室出血は、憩室(粘膜が外側に袋状に突出した状態)の血管が破れて出血する病気です。
憩室そのものは無症状のことが多いですが、その壁が薄いため血管が破れて出血を起こすことがあります。
突然、痛みを伴わずに大量の下血があるのが特徴で、ときに貧血やショック状態に陥ることもあります。
自然止血するケースもありますが、大量出血の場合には内視鏡による止血処置や外科手術が必要になる場合も少なくありません。
再発する可能性もあるため、定期的な経過観察が必要です。
胃や十二指腸にできる潰瘍は、胃酸やピロリ菌、ストレス、薬剤(特にNSAIDs)などが原因で粘膜が傷つき、深くえぐれることで出血を伴うことがあります。
みぞおちの痛みや胸焼け、吐き気などに加えて、黒色のタール便や吐血がみられるのが主な症状です。
出血が続くと貧血になるほか、潰瘍が深く進行することで穿孔を起こし、緊急手術が必要になることもあります。
正確な診断を行うためには胃カメラ検査が有効で、止血処置とともに再発予防の治療が行われます。
胃がんは日本でも依然として罹患率の高いがんのひとつです。
初期は無症状で進行もゆるやかなため、発見が遅れるケースも少なくありません。
進行するとみぞおちの痛みや食欲不振、胃もたれ、吐き気といった症状に加え、出血により黒色便(タール便)や吐血を起こすことがあります。
自覚症状が現れたときにはすでにがんが進行していることもあるため、早期発見のために定期的に胃カメラ検査を受けることが大切です。
治療はがんの進行度に応じて、手術や抗がん剤治療が行われます。

血便や下血が見られた場合は、消化器内科または肛門外科の受診が基本となります。
特に血の色や出方によって原因となる部位が異なるため、症状を詳細に記録しておくことが大切です。
例えば鮮やかな赤い血が便に付着している場合は痔や裂肛など肛門周辺の出血が考えられますが、黒色便であれば胃や十二指腸など上部消化管からの出血の可能性があります。
さらに高熱や腹痛を伴う場合は感染性腸炎の疑いがあるため、速やかに受診が必要です。
血便が少量でも繰り返されるようであれば、大腸がんなどの重大な病気が隠れている可能性も否定できません。
自己判断で様子を見るのは危険なため、少しでも不安がある場合は早めに消化器内科で内視鏡検査を受けることをおすすめします。

便に血が混じる場合の病院での検査方法は、主に以下の5つです。それぞれの内容・特徴や対象となるケース、身体的な負担をまとめました。
| 検査方法 | 内容・特徴 | 主な対象・適応ケース | 身体的負担 |
|---|---|---|---|
| 触診・肛門鏡診察 | ・ゼリー状麻酔を使用し、指と肛門鏡で肛門内を観察
・痔核や裂肛、直腸病変の確認が可能 |
肛門周辺の出血(鮮血) | 非常に軽い |
| 胃カメラ検査 | ・鼻や口からスコープを挿入し、食道・胃・十二指腸を観察
・潰瘍・腫瘍などが見つかれば生検や止血処置も可能 |
黒色便(タール便)、上部消化管出血が疑われる場合 | 中程度(鎮静可) |
| 大腸カメラ検査 | ・肛門からスコープを挿入し、大腸全体の粘膜を観察
・ポリープや潰瘍、がんの発見・切除が可能 |
暗赤色や赤色の血便、大腸がん・炎症性疾患の疑い | 中〜やや重い |
| 腹部CT検査 | ・CT検査で腹部内の臓器や炎症などを確認
・内視鏡だけではわかりにくい異常も補足 |
腹痛を伴う血便、感染症・虚血・憩室炎などの疑い | 中等度(放射線検査) |
| 血液検査 | ・貧血や炎症、感染の有無を確認
・CRPや白血球数などの数値で病態の進行を把握可能 ・出血量や炎症性腸疾患の補助診断に有効 |
出血量の把握、炎症・感染症・IBD(炎症性腸疾患)の疑い | 極めて軽い |

血便と聞くと深刻な病気を疑って不安になる方も多いですが、すべての血便が重篤な病気につながるわけではありません。
例えばいきみすぎや硬い便によって肛門周辺が切れて出血する裂肛(切れ痔)や、排便時に痔核(いぼ痔)が刺激されて出血するケースは、比較的よくあるものです。
これらは鮮やかな赤い血が便の表面や紙に付着することが多く、出血量も少ないのが特徴です。
痔核や裂肛が原因の場合は、日常生活の中で排便習慣や食生活を整えることで改善することもあります。
ただし、同じような症状でもまれに大腸がんや腸の病気が隠れている場合があるため、「痛みがない」「毎回ではない」といった理由で放置するのは危険です。
特に出血が繰り返される場合や、色が黒っぽい、粘液が混じる、下痢や腹痛を伴うといった場合には、一度医療機関を受診しましょう。
便に血が混じる症状は、痔や裂肛のように過度に心配する必要のないケースもある一方で、大腸がんや潰瘍性大腸炎、感染性腸炎など重大な病気が原因になっていることもあります。
血便の色や出方、他の症状の有無によって出血の場所や緊急度をある程度判断できますが、自己判断には限界があります。
出血が繰り返される、黒色便が出る、発熱や腹痛を伴うなどの場合は、早めの受診が必要です。
えさか駅前にしごりおなかとおしりのクリニックでは、お腹やお尻に関する症状に対応しています。
お尻の手術や治療もできるため、血便や下血などの症状にお悩みの方は、ぜひ当院までご相談ください。