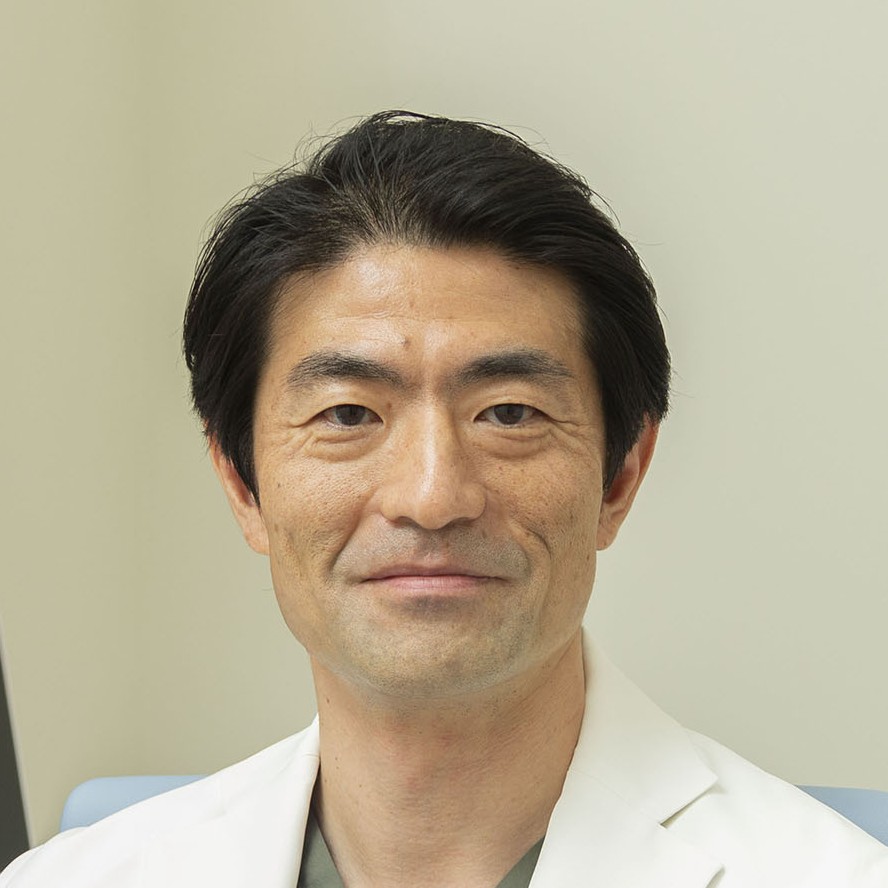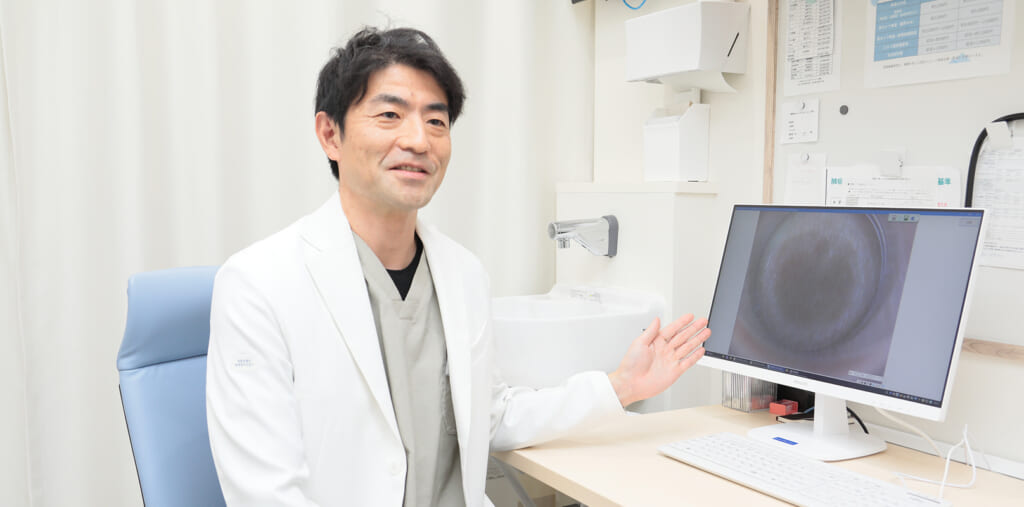お腹が張る症状は日常的に誰でも経験しますが、原因はさまざまです。食べ過ぎや便秘、ストレスといった生活習慣によるものから、消化器や婦人科系の病気が隠れていることもあります。張り方の種類によって原因や対処法も異なるため、正しい知識を持つことが大切です。
本記事では、お腹の張りの種類・原因・考えられる病気・対処法・受診先まで幅広く解説します。
本記事でわかること
- お腹の張り方の2つのタイプとその特徴
- 生活習慣による主な原因
- 張りの背後にある可能性のある病気
- 具体的なセルフケアと対処法
- 受診すべき診療科と検査内容
お腹の張り方は2種類ある

お腹の張りには大きく分けて『ガスが溜まって生じるもの』と『胃部膨満感によって生じるもの』の2種類があります。
それぞれの原因と感じ方の違いは以下の通りです。
| お腹の張り方の種類 | 主な原因 | 感じ方・症状例 |
|---|---|---|
| ガスが溜まって生じる張り | 腸内環境の乱れ、悪玉菌の増加、便秘など | お腹全体がパンパンに膨らむ、ガスが溜まって苦しい、下腹部が張る、おならの回数が多い |
| 胃部膨満感によって生じる張り | 食べ過ぎ、胃の運動低下、呑気症など | 胃のあたりが重い、膨らんだ感じがする、げっぷが多い、食後の不快感が強い |
ガスによる張りは、腸内に気体が過剰に溜まることで起こります。
これは食生活の乱れやストレスによる腸内細菌のバランス崩れが大きな原因です。
一方、胃部膨満感は食べすぎや呑気症(空気を飲み込みすぎてしまう病気)によって胃に空気や食べ物が滞り、胃の上部に不快感が生じます。
どちらの張りも日常的に起こり得る不快症状ですが、長引く場合は消化器疾患や内臓疾患の可能性もあるため注意が必要です。
お腹が張る主な原因

お腹が張る原因として、まずは主に5つが挙げられます。整理すると以下の通りです。
| 原因 | 詳細 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| 食事(暴飲暴食、肉類やにんにくの食べ過ぎ) | -食べ過ぎで空気を飲み込みやすい
-肉やにんにくでガスが発生しやすい |
-食事内容の偏りに注意する
-食べ過ぎ・早食いを控える |
| 便秘 | 便が溜まりガスが発生・滞留しやすい | -慢性便秘は腸内環境悪化に直結する
-食物繊維や水分摂取が重要になる |
| 運動不足 | 腸の動きが弱まりガスが溜まる | -デスクワーク中心の人は要注意
-軽い運動・ストレッチが有効 |
| ストレス | 自律神経が乱れ腸の動きが不安定になる | -ストレス管理が重要
-リラックス時間を確保する |
| 女性特有の原因 | -ホルモン変化で腸の動きが低下
-婦人科疾患でも膨満感 |
-婦人科系疾患の可能性も考慮する
-症状が続くなら婦人科受診も検討する |
加えて注意したいのは、病気の影響によるものです。次の章で詳しく解説します。
お腹が張る原因となる病気
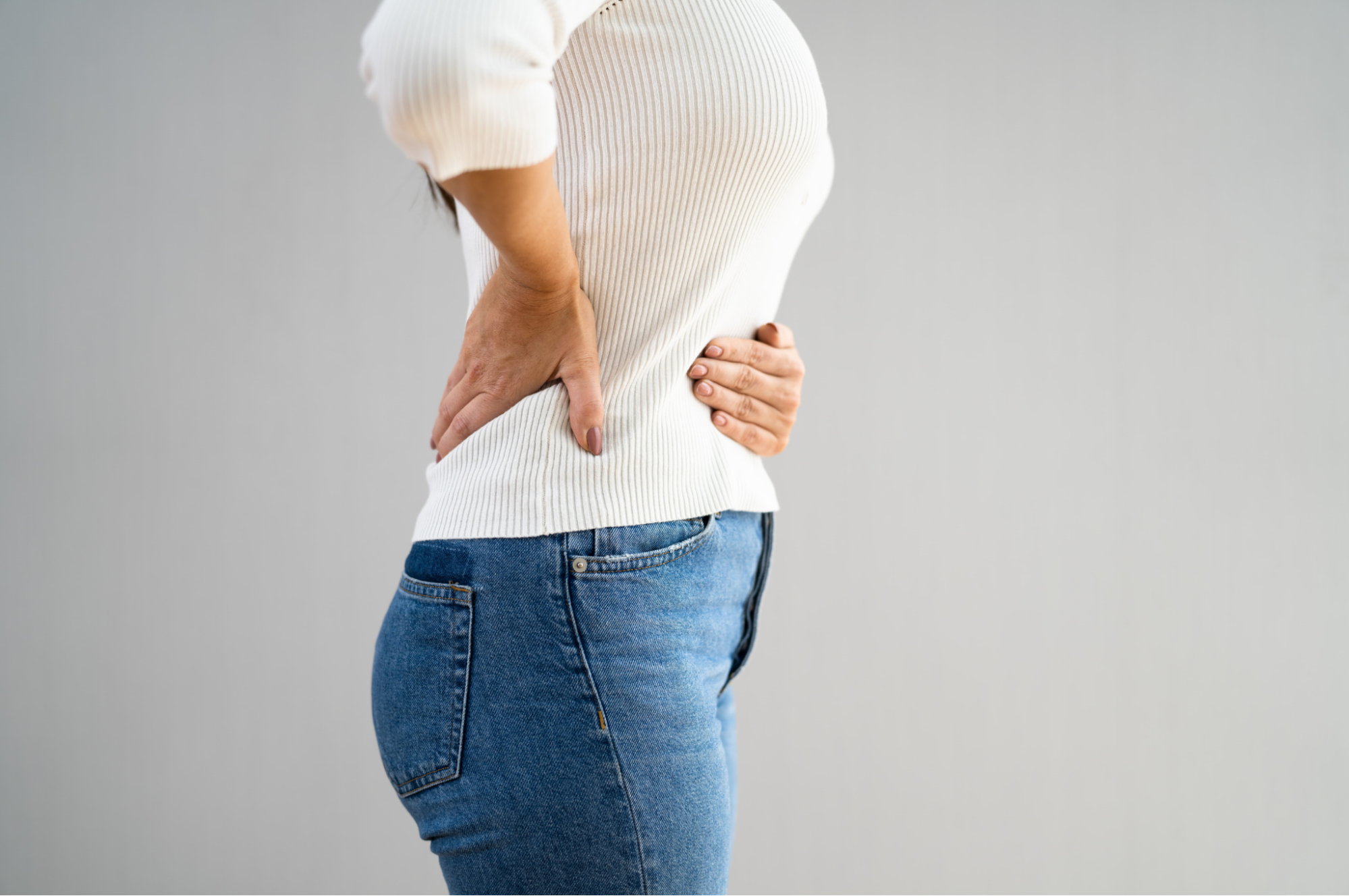
お腹が張る原因となる病気として、以下が挙げられます。
- 過敏性腸症候群
- 炎症性腸疾患
- 腸炎
- 腹水
- 腹部の腫瘍(胃がん、大腸がん、膵臓がん、卵巣腫瘍など)
- 腸閉塞
- 機能性ディスペプシア
- 逆流性食道炎
- 慢性胃炎
- 急性胃腸炎
- 呑気症
それぞれ詳しく解説します。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群は、腸に炎症や潰瘍などの器質的な異常がないにもかかわらず、下痢や便秘、腹痛といった症状が慢性的に続く病気です。
主にストレスや不安、生活リズムの乱れなどが引き金となって発症するとされ、腸のぜん動運動に異常が生じます。
代表的な症状には腹痛や下痢・便秘の繰り返し、お腹の張り、排便後の不快感や残便感などがあり、症状が日常生活に支障をきたす場合も少なくありません。
まためまいや頭痛、吐き気などの全身症状を伴うこともあります。
3日以上続く腹痛や不快感とともに、排便によって症状が軽減するなどの特徴がみられる場合は、過敏性腸症候群が疑われます。
炎症性腸疾患
炎症性腸疾患は、腸の粘膜に慢性的な炎症が起こる病気で、代表的なものに潰瘍性大腸炎とクローン病があります。
いずれも厚生労働省の難病指定を受けており、免疫の異常が関与していると考えられている病気です。
症状は人によって異なりますが、主に腹痛、下痢、血便、体重減少、全身の倦怠感などが挙げられます。
腸炎
腸炎はウイルスや細菌、寄生虫などによる感染や、食あたり、抗生物質の副作用などによって発生する腸の炎症です。
急性腸炎の場合は突然の腹痛や下痢、発熱、吐き気・嘔吐などの症状を伴い、数日間で自然に治まることが多いですが、症状が強い場合や長引く場合は注意が必要です。
炎症により腸内のガスの通りが悪くなると、お腹の張りを強く感じるようになります。
なかには血便がみられるケースもあり、特に高齢者や免疫力が低下している人では重症化するリスクもあるため、上記の症状が現れたら早めに医療機関を受診しましょう。
腹水
腹水とは、肝硬変やがん、炎症性疾患などを原因として、腹腔内に液体が過剰に溜まってしまう状態です。
初期段階では自覚症状がほとんどありませんが、進行すると腹部の膨満感や張り、体重増加、息苦しさなどが現れてきます。
腹水が多量に溜まると、腸や胃を圧迫し、消化不良や食欲不振の原因にもなります。
腹部の違和感が続く場合は、早めに検査を受けましょう。
腹部の腫瘍(胃がん、大腸がん、膵臓がん、卵巣腫瘍など)
お腹の張りを引き起こす原因の一つとして、腹部の臓器に発生する腫瘍が挙げられます。
例えば胃がんや大腸がんが進行すると、腫瘍が腸管を圧迫してガスや便の通過を妨げ、腹部の膨満感を引き起こします。
大腸がんでは、便秘と下痢の繰り返し、血便、便が細くなるなどの症状を伴うこともあるため、張りと同時にこれらの変化がみられる場合は注意が必要です。
女性では卵巣腫瘍も張りの原因になり得ます。
初期は無症状でも、腫瘍が大きくなることで下腹部が圧迫され、違和感や膨らみを覚えるようになります。
がんは早期発見が重要なため、定期的に内視鏡検査を受けることが大切です。
腸閉塞
腸閉塞は、何らかの原因により腸が詰まり、腸の中の内容物が正常に移動できなくなる重篤な病気です。
原因としては、手術後の癒着やヘルニア、腫瘍、腸のねじれ、胆石などさまざまなものがあり、症状は急激に悪化することが多いです。
腸が詰まるとガスや腸液が溜まり、強い腹部膨満感が生じます。
また激しい腹痛や吐き気、嘔吐、排便・排ガス困難、発熱などを伴うこともあります。
腸閉塞は自然に治ることはなく、放置すると腸が壊死するおそれもあるため、緊急性の高い状態です。
お腹の張りが強く、上記のような症状が見られる場合は速やかに医療機関を受診しましょう。
機能性ディスペプシア
機能性ディスペプシアは、内視鏡などの検査で明らかな異常が見つからないにもかかわらず、胃やみぞおちの不快感が慢性的に続く病気です。
主な症状は食後の膨満感や胃のもたれ、腹部の張り、みぞおちの痛みなどで、精神的ストレスや胃の運動機能の低下、胃酸分泌の異常などが関与していると考えられています。
症状は一時的なものではなく、数週間から数か月にわたり繰り返すことが多く、日常生活にも大きく影響します。
逆流性食道炎
逆流性食道炎は、胃酸が食道に逆流することによって、胸やけや喉の違和感、げっぷ、咳、お腹の張りといった症状を引き起こす病気です。
胃の中の圧力が高まることで、ガスが食道へ押し戻されやすくなり、結果としてお腹の張りや膨満感が目立つようになります。
慢性的な胸やけや張りがある場合は、逆流性食道炎の可能性が考えられるでしょう。
市販薬で一時的に症状が和らぐこともありますが、繰り返すようであれば医療機関での診断・治療が必要です。
慢性胃炎
慢性胃炎は、胃の粘膜が長期的に炎症を起こしている状態です。
主な原因はピロリ菌の感染や、過剰な飲酒・喫煙、ストレス、長期間の薬剤使用などです。
胃の炎症が慢性的に続くと、消化機能が低下し食べ物が長く胃に留まるため、げっぷやお腹の張り、胃もたれといった症状が出やすくなります。
お腹の張り以外にも、胃痛や吐き気、胸焼けなどを伴うこともあり、食後に強い不快感を感じることが多くなります。
慢性胃炎を放置すると、胃潰瘍や胃がんのリスクが高まるため、早期診断と適切な治療が大切です。
急性胃腸炎
急性胃腸炎はウイルスや細菌の感染、または薬の副作用などにより、胃や腸の粘膜に急激な炎症が起こる病気です。
代表的な原因としてはノロウイルスやロタウイルス、サルモネラ菌などがあります。
主な症状は腹痛や下痢、吐き気、嘔吐、発熱、腹部膨満感、食欲不振などです。
炎症があると腸の動きが一時的に低下するため、ガスの排出がうまくいかず、張りが悪化します。
重症化すると点滴や入院治療が必要になることもあります。
急性症状が強く現れるため、体調の急変には注意が必要です。
呑気症
呑気症は、空気を過剰に飲み込んでしまうことで胃腸にガスが溜まり、お腹の張りやげっぷ、頻繁なおならといった症状が現れる状態です。
早食いや緊張などにより、無意識に空気を大量に飲み込んでしまうのが主な原因です。
特にストレスや不安の強い人に多く見られ、心因性の側面も強い病気といえます。
ゆっくり食事をする、口呼吸を避ける、ストレスマネジメントを行うといった生活習慣の見直しが有効です。
症状が続く場合は、内科や心療内科での相談を検討すると良いでしょう。
お腹が張るときの対処法

お腹が張るときの対処法として、以下の5つが挙げられます。
- 規則正しい食習慣と栄養のバランスのいい食事
- 生活習慣を改善して自律神経を整える
- 適度に運動する
- ストレスをため込まない
- 市販薬を試してみる
ここでは上記5つの対処法についてそれぞれ解説します。
規則正しい食習慣と栄養のバランスのいい食事
お腹の張りを防ぐには、食事内容の見直しが基本です。暴飲暴食や早食いは空気を多く飲み込み、ガスが溜まりやすくなります。また脂っこい料理や刺激物も腸に負担をかけます。
・ポイント
- 1日3食、規則正しく食事を摂る
- 早食いを控え、ゆっくりよく噛んで食べる
- 脂っこい食事・刺激物を控えめに
- 発酵食品・食物繊維・乳酸菌を積極的に摂取
おすすめの食品
| 食品群 | 具体例 |
|---|---|
| 発酵食品 | 納豆、ヨーグルト、キムチ |
| 食物繊維 | 野菜、果物、全粒穀物、海藻 |
| 乳酸菌飲料 | ヨーグルトドリンク、乳酸菌サプリ |
生活習慣を改善して自律神経を整える
自律神経は腸の働きをコントロールしています。不規則な生活や睡眠不足は腸のぜん動運動を妨げ、ガスが溜まりやすくなります。
・改善のポイント
- 毎日同じ時間に寝起きする
- 睡眠は十分にとる(7〜8時間目安)
- 湯船にゆっくり浸かる
- 深呼吸や瞑想を取り入れる
適度に運動する
運動は腸の動きを活発にし、ガスの排出を助けます。特に座りっぱなしの生活を送る人は意識的に体を動かすことが重要です。
・おすすめの運動
- 1日30分のウォーキング
- 軽いジョギング
- ヨガやピラティス
腸に効く簡単なストレッチ
| ストレッチ方法 | やり方 |
|---|---|
| お腹ねじりストレッチ | 仰向けで膝を倒して左右にゆっくり倒す |
| 腹部マッサージ | おへその周囲を「の」の字に軽くマッサージ |
ストレスをため込まない
ストレスは腸の働きを乱し、膨満感を悪化させます。日常的にストレスを解消する習慣を取り入れることが大切です。
・リフレッシュ方法
- 趣味の時間をつくる
- 軽い運動や散歩をする
- 自然に触れる
- 深呼吸・瞑想を行う
- 信頼できる人と話す
ストレス軽減に役立つ習慣
| 方法 | 効果 |
|---|---|
| 音楽を聴く | 緊張緩和・気分転換 |
| アロマを使う | リラックス効果 |
| 日記を書く | 気持ちの整理 |
市販薬を試してみる
軽度の症状なら市販薬を利用するのも選択肢の一つです。ただし症状が続く場合は医師に相談しましょう。
・市販薬の種類
- 消泡剤(ガス溜まりの改善)
- 整腸剤(乳酸菌・ビフィズス菌)
- 消化薬(消化促進)
・使用時の注意
薬の効果は個人差があります。説明書をよく読み、用法・用量を守りましょう。改善しない場合や他の症状があるときは自己判断せず、医師に相談することが大切です。
検査を受けるなら何科に受診すべき?

お腹の張りが続く場合、まず受診すべきは『消化器内科』もしくは『内科』です。
特に吐き気や下痢、便秘、胃もたれ、食欲不振といった胃腸に関する症状を伴っているときは、消化器内科が適しています。
消化器内科では胃内視鏡検査や大腸内視鏡検査、腹部超音波、CT検査などによって、胃腸や肝臓、膵臓、大腸などの状態を詳しく調べられます。
しかしお腹の張りは女性特有の原因で生じていることもあるため、女性で妊娠の可能性がある場合や月経周期との関係がありそうな場合は、『産婦人科』の受診を検討しましょう。
まとめ
お腹の張りは食生活やストレス、運動不足といった生活習慣が原因の場合もあれば、消化器疾患や婦人科系の病気など、病院での専門的な治療が必要となるケースもあります。
特にお腹の張りが長引いたり、他の症状を伴ったりする場合は、自己判断で放置せず、消化器内科などの専門科で検査を受けることが大切です。
えさか駅前にしごりおなかとおしりのクリニックでは、肛門外科・消化器内科・胃腸科の専門的な診療に対応しており、全医師が日本内視鏡学会専門医、消化器病学会専門医を有し、安全で質の高い大腸カメラ検査を行っています。
また便の乱れや便秘、便失禁に対しても日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会評議員、大腸肛門機能障害研究会世話人である錦織院長が骨盤底筋専門外来で診療を行っています。
胃・大腸内視鏡検査の同日検査も可能なため、お腹の張りをはじめとした気になる症状がある方はぜひ当院までご相談ください。