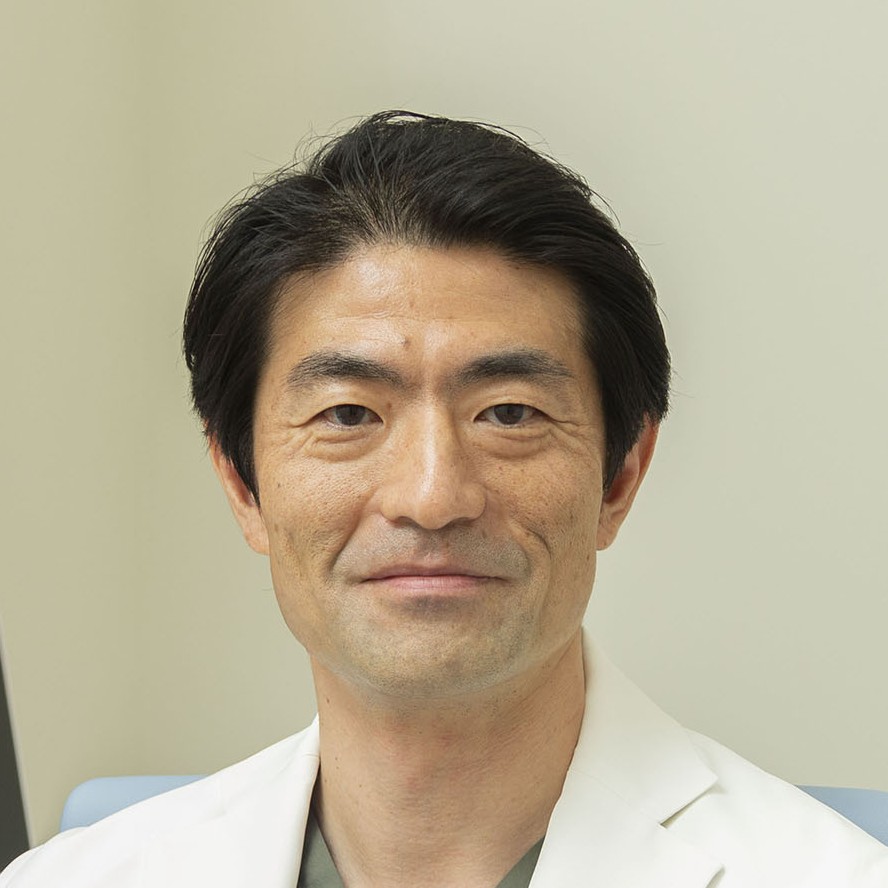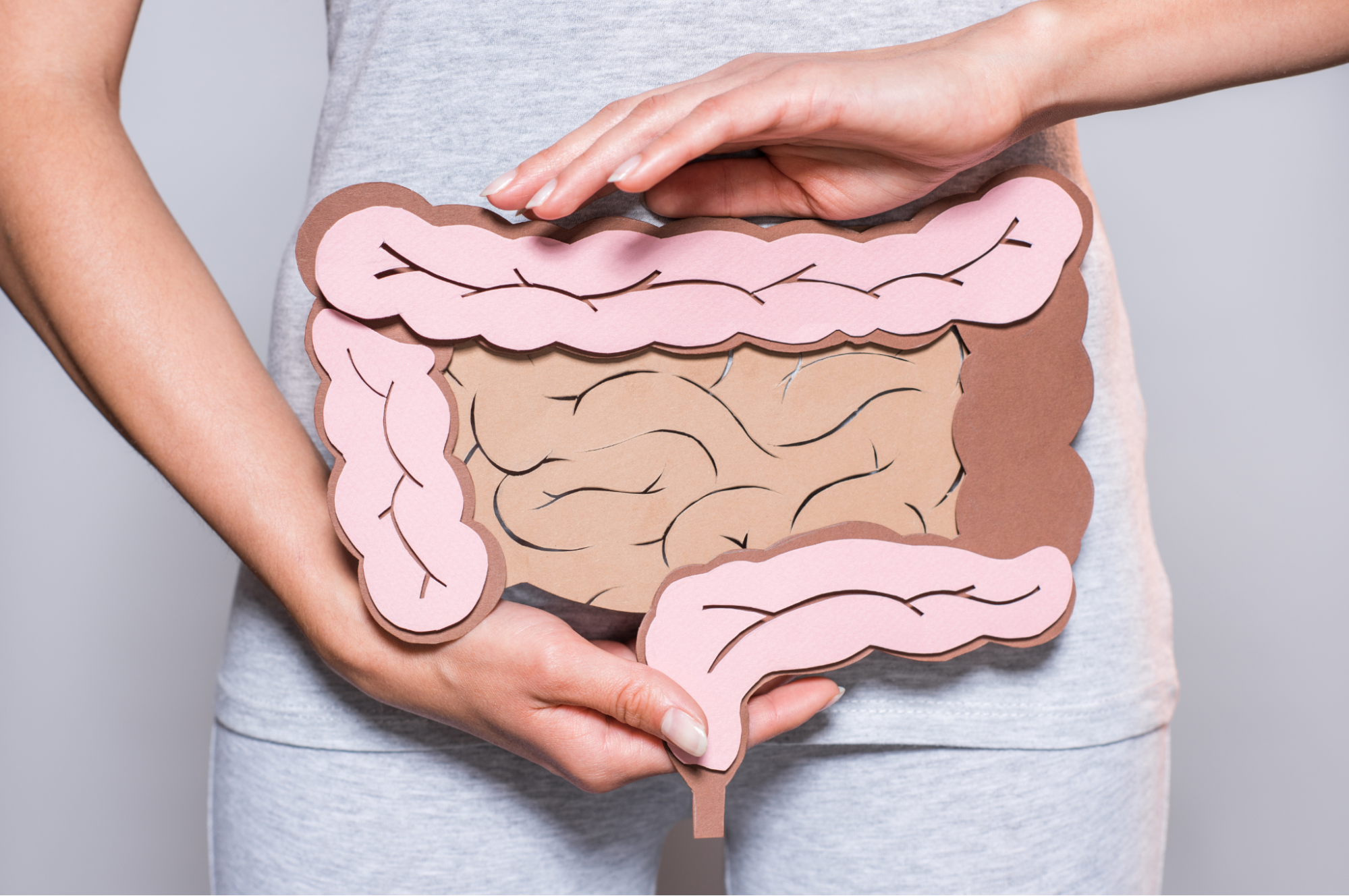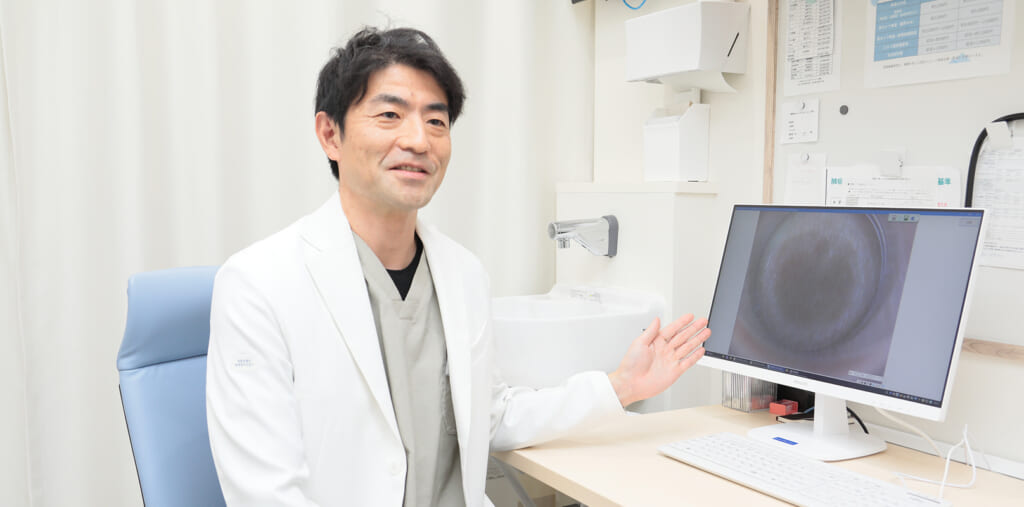大腸がんは、日本人のがん罹患数・死亡数ともに上位に位置し、早期発見が治療成績に大きく影響します。その早期発見のために有効とされているのが、大腸内視鏡検査です。便通異常(便秘・下痢・血便)や腹痛、急な体重減少、家族に大腸がんの既往がある方、ポリープの切除歴がある方、40歳以上で食生活が乱れている方などは、大腸内視鏡検査を受けたほうがよい対象に該当します。
本記事では、次の点について詳しく解説します。
- 大腸内視鏡検査を受けた方がいい人の特徴と症状
- 検査を受けるべき頻度(症状別・年齢別)
- 検査で発見できる疾患とその重要性
- より楽に検査を受けるための方法
検査を迷っている方や、どのタイミングで受けるべきか判断に迷っている方にとって、正しい判断の手助けとなる情報を網羅しています。
大腸内視鏡検査を受けた方がいい人の症状・特徴

大腸内視鏡検査を受けた方がいい人の症状・特徴として、以下が挙げられます。
- 便通異常がある人
- 腹痛や吐き気がある人
- 急激に体重が減った人
- 炎症性腸疾患がある人
- 大腸ポリープが見つかったことがある人
- 親族で大腸がんになった人がいる人
- 40歳以上の人
- 食生活が乱れている人
- 健康診断で「要再検査」「要精密検査」となった人
ここでは上記9つの症状・特徴についてそれぞれ解説します。
便通異常がある人
便秘や下痢、残便感、粘液便など便通の異常が続いている場合は、大腸に何らかのトラブルが起きている可能性があります。
特に「下痢と便秘を繰り返す」「排便してもスッキリしない」「便に血や粘液が混ざる」といった症状は、炎症やポリープ、大腸がんなどが原因の場合もあります。
通常の便はバナナ状で排便もスムーズですが、上記のような異常が見られるときは注意が必要です。
見逃されやすい症状ではありますが、長引く場合には早めに大腸内視鏡検査を受けることが望ましいでしょう。
腹痛や吐き気がある人
腹痛や吐き気が続く場合、大腸に異常が生じている可能性があります。
特に、下腹部の膨満感やおならが出ないなどの症状がある場合は、腸閉塞やがんによる腸の狭窄が疑われます。
また腹痛だけでなく吐き気を伴うこともあり、食欲不振や体重減少につながるケースもあります。
原因不明の腹痛や吐き気が慢性的に続く場合は、症状が軽度であっても放置せず、大腸内視鏡検査を受けて原因を調べることが大切です。
急激に体重が減った人
ダイエットをしていないのに6ヶ月以内に体重が5%以上減少している場合は、何らかの疾患による可能性があります。
大腸がんなどの悪性腫瘍では、がん細胞が栄養を奪うことで体重が減ることがあるため、注意が必要です。
また潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患でも、腹痛や下痢が原因で食事がとれず、体重が減少することがあります。
若年層でもこうした病気は見られるため、急激な体重変化がある場合は大腸内視鏡検査で正確な診断を受けることが大切です。
炎症性腸疾患がある人
潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患がある場合は、大腸内視鏡検査を受けた方が良いでしょう。
これらの病気は慢性的に腸に炎症を起こすもので、下痢や血便、持続する腹痛などの症状が見られます。
進行すると発熱や貧血、体重減少といった全身症状も出てくるため、日常生活に支障をきたすこともあります。
内視鏡検査は腸の状態を詳しく観察し、炎症の程度や病変の範囲を確認することが可能です。
診断や治療経過の確認にも役立つ重要な検査のため、積極的に受けましょう。
大腸ポリープが見つかったことがある人
過去に大腸ポリープが見つかった経験がある人は、再発やがん化のリスクを避けるために、定期的に内視鏡検査を受けた方が良いでしょう。
大腸ポリープには「腫瘍性」と「非腫瘍性」があり、特に腫瘍性ポリープは大腸がんに進行する可能性があります。
このポリープは切除後も再発しやすいため、経過観察が欠かせません。
病理検査でがん化のリスクが高いタイプと判定された場合は、医師の指示のもと、定期検査を受けるようにしましょう。
親族で大腸がんになった人がいる人
親族に大腸がんを患った人がいる場合、自身も発症リスクが高まることが分かっています。
両親や兄弟姉妹といった近親者だけでなく、祖父母や叔父・叔母、いとこなどの親族に大腸がん患者がいる場合も注意が必要です。
遺伝子に関連する「家族性大腸腺腫症」などの疾患がある場合は、大腸ポリープが多発し、若い年齢でがんを発症するリスクもあります。
このような家族歴のある場合は、40代以前からでも定期的に大腸内視鏡検査を受けることが推奨されています。
定期的に検査を受け、自覚症状がないうちに異常を見つけることが大切です。
40歳以上の人
大腸がんは年齢とともに発症リスクが高まるため、40歳を過ぎたら定期的に検査を受けた方がいいとされています。
特に50歳を超えると発症率が一気に上がる傾向にあり、男女問わず注意が必要です。
また、大腸がんは初期症状が出にくい病気でもあります。
進行するまで気づかないケースが多く、症状が出てからでは治療の選択肢が限られる可能性もあります。
女性はがんによる死亡原因の第1位が大腸がんとなっているため、「自分は大丈夫」と考えてしまうのは危険です。
便通異常や便潜血がみられた場合は、迷わず大腸内視鏡検査を受けましょう。
食生活が乱れている人
食生活の乱れは、大腸の健康に大きな影響を与えます。
特に赤身肉(牛・豚など)や加工肉(ソーセージ・ハム・ベーコンなど)の摂取が多く、野菜や食物繊維が不足している人は、大腸がんのリスクが高まるとされています。
さらにアルコールの過剰摂取や脂っこい食品の多用も腸内環境を悪化させ、発がんリスクを上げる要因となるため注意が必要です。
このような食生活が続いている人は、自覚症状がなくても腸に何らかの異常が生じている可能性があります。
早期発見と予防のためにも、定期的に大腸内視鏡検査を受けましょう。
健康診断で「要再検査」「要精密検査」となった人
健康診断の結果で「要再検査」や「要精密検査」の指摘を受けた場合は、その時点で異常の可能性があります。
特に便潜血検査で陽性が出たり、CEAやCA19-9といった腫瘍マーカーの数値が基準を超えていたりした場合は、大腸内視鏡検査での詳しい確認が必要です。
重大な病気が潜んでいる可能性も否定できないため、症状がないからといって自己判断で放置するのは危険です。
検査を受けて原因を明確にし、必要に応じて適切な対応を行いましょう。
【症状別】大腸内視鏡検査を受ける適切な頻度

大腸内視鏡検査を受ける適切な頻度は、症状によって異なります。
| 症状 |
大腸内視鏡検査を受ける頻度 |
| 血便が出る場合 |
すぐに検査を受け、異常がなければ2~3年に1回 |
| 大腸ポリープを切除したことがある場合 |
1〜3年に1回 |
| 大腸がんの治療をした場合 |
1年に1回 |
| 慢性的に下痢が出る場合 |
1年に1回 |
| 前回の大腸内視鏡検査で異常がなかった場合 |
5年に1回 |
ここでは上記の症状別に、大腸内視鏡検査を受ける適切な頻度について解説します。
血便が出る場合
血便が出る場合は、なるべく早めに医師へ相談し、必要に応じて大腸内視鏡検査を受けるべきです。
血便の原因は痔や裂肛といった良性のものから、大腸がんやポリープなどの重篤な疾患まで幅広く、見た目だけでは判断できません。
特に便に血が混ざっていたり、便の周囲に血が付着していたりする場合は要注意です。
初回検査で異常がなかったとしても、2〜3年に1回の頻度で定期的に検査を受けることが望ましいでしょう。
2回続けて問題がなければ、医師の判断で5年に1回まで間隔を空けても問題ありません。
自己判断で放置せず、必ず医師の診断を受けることが大切です。
大腸ポリープを除去したことがある場合
過去に大腸ポリープを除去したことがある場合は、再発のリスクを考慮して定期的な検査が必要です。
ポリープの種類や大きさ、個数によっても推奨される検査頻度が異なりますが、1〜3年に1回の頻度を目安とするといいでしょう。
小さなポリープが1〜2個程度であれば3~5年ごとでも問題ないこともありますが、大きなポリープや複数のポリープが見つかった場合は、1年ごとの検査が必要になることもあります。
またすべてのポリープを一度で取りきれなかった場合には、3〜6ヶ月後の再検査を行い、その後も経過観察を行います。
医師と相談のうえ、自分に合った頻度で定期的に検査を受けることが大切です。
大腸がんの治療をした場合
大腸がんの治療を受けたことがある方は、術後の経過観察として年に1回の大腸内視鏡検査が推奨されます。
大腸がんは異なる部位に新たながんが発生しやすい性質があり、治療後も油断はできません。
再発や新たながんの早期発見を目的として、計画的な検査スケジュールを組む必要があります。
特に手術後5年間は再発リスクが高いため、少なくとも年1回は検査を受けましょう。
定期検査を怠ると再発を見逃してしまうリスクもあるため、医師の指示に従い、必ず検査を継続することが大切です。
慢性的に下痢が出る場合
下痢が1カ月以上続いているような慢性下痢の症状がある場合には、大腸内に炎症やポリープ、がんなどが潜んでいる可能性があります。
特に炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)などが疑われる場合は、診断と経過観察のために定期的な大腸内視鏡検査が必要です。
初回の検査で病変が発見された場合は、治療方針の決定やその後の経過確認としても活用されます。
明確な異常が見つからなかった場合でも、症状が続くようであれば年1回の検査を目安に、必要に応じて医師の判断で検査頻度を調整します。
原因不明の下痢は放置せず、なるべく早めに病院を受診しましょう。
前回の大腸内視鏡検査で異常がなかった場合
以前に大腸内視鏡検査を受けて異常がなかった場合でも、それで一生安心というわけではありません。
ポリープやがんは数年単位で新たに発生することがあるため、基本的には5年に1回程度定期的に検査を受けることが推奨されます。
特に家族歴がある方や食生活・生活習慣に不安がある方は、間隔を空けすぎず、医師と相談して適切なタイミングで検査を受けましょう。
自覚症状がなくても定期的に検査を受けることで、病気の早期発見・早期治療につながります。
【年齢別】大腸内視鏡検査を受ける適切な頻度

大腸内視鏡検査は、年齢によって受けるべき頻度が異なります。
特に40代以降は大腸がんのリスクが急激に高まるため、定期的に検査を受けることが大切です。
以下に年代別の適切な検査頻度の目安をまとめました。
| 年代 |
検査頻度の目安 |
| 40代 |
3年に1回(未検査の場合は早めに初回検査を受ける) |
| 50代 |
3年に1回(腺腫の既往がある場合は年1回) |
| 60代 |
3年に1回 |
| 70代以上 |
医師と相談のうえ決定 |
40歳以上でまだ検査を受けたことのない人は、なるべく早めに初回検査を受けましょう。
初回検査で特に異常がみられなければ、3年に1回の頻度で定期的に検査を受けることが望ましいです。
また上記に該当する年齢の人でも、ポリープを切除した経験がある場合は、年1回の頻度が推奨されます。
70代以上は体調や体力を考慮しつつ、医師と相談して検査の必要性を判断しましょう。
定期的に大腸内視鏡検査を受けた方がいい理由

大腸内視鏡検査を定期的に受ける最大の理由は、大腸がんの早期発見と予防につながるためです。
大腸がんは初期の段階では自覚症状がほとんどなく、便に血が混じる、腹痛があるといった症状が出たときには、すでに進行がんになっているケースも少なくありません。
進行がんになると、治療には開腹手術や抗がん剤が必要になる可能性が高く、身体的・精神的負担も大きくなってしまいます。
しかし早期に見つけられれば、内視鏡による切除で治療が完結することも多く、生活への影響も小さく抑えられます。
さらに大腸内視鏡検査ではがんだけでなく、がんの前段階といえる大腸ポリープも発見・切除することが可能です。
ポリープの段階で取り除くことで、将来がんに進行するリスクを事前に防ぐことができます。
検査のハードルが高いと感じている方も多いですが、それを理由に検査を避けてしまうと、病気の発見が遅れてしまう恐れがあります。
無症状のうちから定期的に検査を受けることで、手遅れになる前に対処することが可能です。
大腸内視鏡検査でわかること
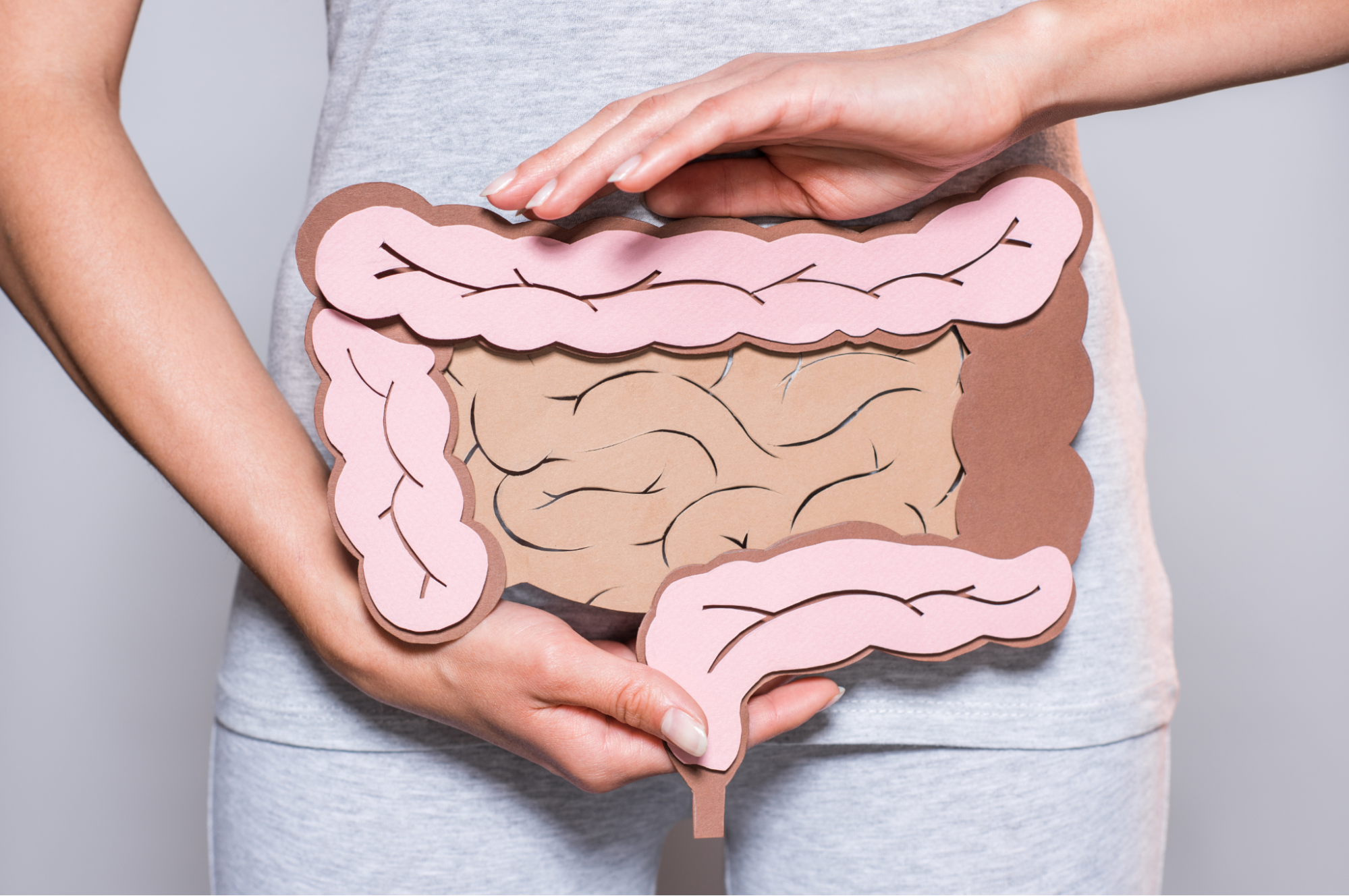
大腸内視鏡検査は早期の大腸がんや、がんの前段階である大腸ポリープなど、症状が出にくい疾患の発見に非常に役立ちます。
大腸内視鏡検査でわかる代表的な病気は以下の通りです。
- 早期大腸がん
- 進行大腸がん
- 大腸ポリープ
- 粘膜下腫瘍
- 大腸憩室症
- 潰瘍性大腸炎
- 直腸潰瘍
- 大腸脂肪腫
- 大腸メラノーシス
これらの中でも特に重要なのが、早期大腸がんと大腸ポリープの発見です。
大腸がんは進行してから見つかると手術や抗がん剤治療が必要になりますが、ポリープの段階で切除できればがん化を未然に防げます。
進行するまで症状が出にくいため、無症状のうちから定期的に検査を受けることが大切です。
特にリスクの高い40代以上の方や便に異常が見られた方、家族に大腸がんの既往がある方などは、早めに検査を受けましょう。
楽に大腸内視鏡検査を受ける方法

楽に大腸内視鏡検査を受ける方法として、具体的に以下が挙げられます。
| 楽に検査を受ける方法 |
理由 |
| 内視鏡検査専門医が在籍する病院を選ぶ |
豊富な実績と技術を持つ専門医が在籍する病院を選ぶことで、検査中の苦痛を抑えやすくなる |
| 鎮静剤を使用する |
鎮静剤を使用することでウトウトとした状態で検査を受けられるため、挿入時の違和感やお腹の張りを感じにくくなる |
| 苦痛の少ない挿入法で検査を受ける |
『軸保持短縮法』や『水浸法』といった苦痛の少ない挿入法で検査を受けることで、お腹の張りや痛みが軽減される |
| リラックスした状態で検査を受ける |
緊張して力が入ると内視鏡が進みにくくなり、かえって苦痛の原因となるため、深呼吸や軽いストレッチなどによりリラックスした状態で検査を受ける |
大腸内視鏡検査は、「痛そう」「つらそう」といった不安から受診をためらう方も少なくありません。
しかし近年は医療技術の進歩と工夫により、苦痛を大きく軽減した検査が可能になっています。
さらに上記のような方法も合わせることで、より快適に大腸内視鏡検査を受けられます。
不安な場合は事前に医療機関に相談し、自分に合った方法で検査を受けましょう。
- あわせて読みたい
-
大腸内視鏡検査が痛い人の特徴は?痛みを軽減する方法についても解説
大腸内視鏡検査で生じる痛みの原因
個人差はありますが、大腸内視鏡検査では痛みを感じることがあります。
以下の3つが主な原因です。
痛みの原因
内容
大腸が引き伸...
まとめ
大腸内視鏡検査は、大腸がんやポリープを早期発見・予防するために有効な検査です。
特に便通異常が続いている人や親族に大腸がんになった人がいる人、40歳以上の人、過去にポリープを切除した経験がある人などは、定期的に検査を受けることが推奨されます。
内視鏡専門医の在籍する医療機関を選んだり、鎮静剤を活用したりすることで、検査の負担を大きく軽減することも可能です。
「まだ症状がないから大丈夫」と油断せず、自分の年齢や体調、家族歴に応じて、適切なタイミングで検査を受けましょう。
えさか駅前にしごりおなかとおしりのクリニックでは、苦痛や不安に配慮した大腸内視鏡検査を行っています。
鎮静剤を使用することで検査時の痛みを軽減できるため、検査中の苦痛が不安で受診をためらっている方は、ぜひ当院までご相談ください。