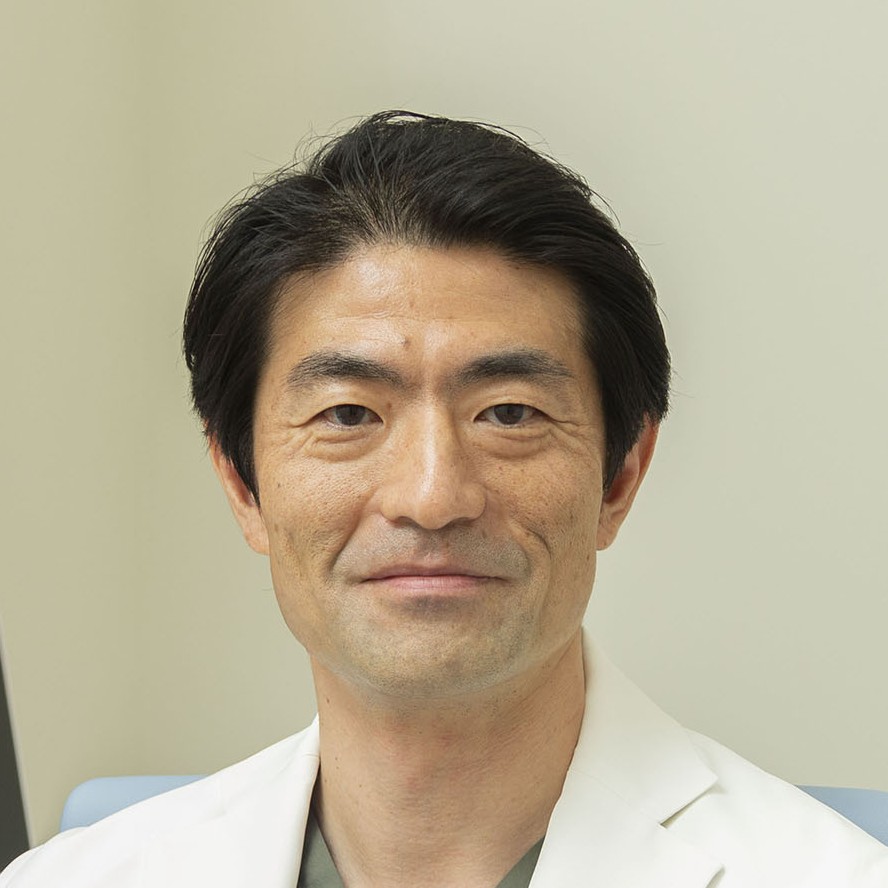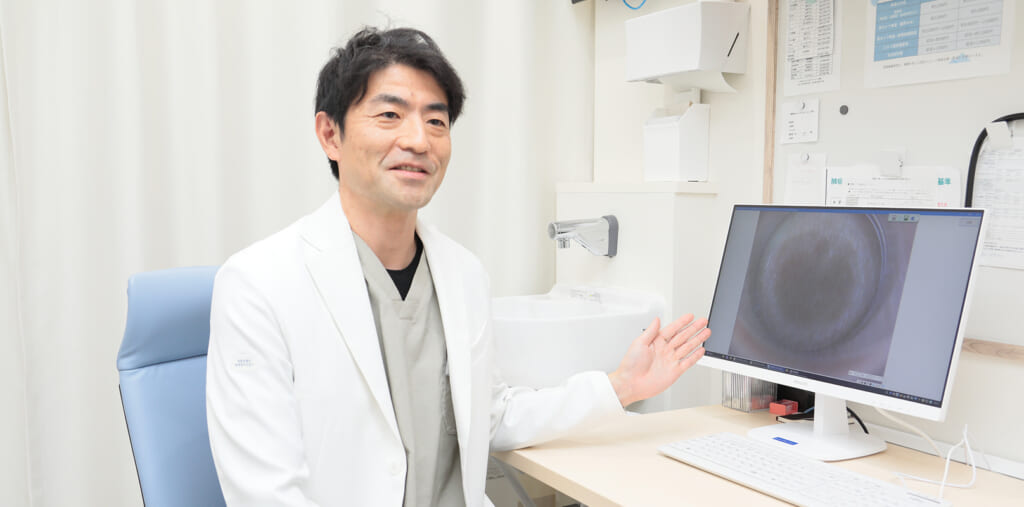「最近おならの回数が増えた」「においがきつくなった気がする」──そんな変化に、大腸がんとの関係を疑って不安になる方もいるかもしれません。
結論からいえば、おならの変化だけで大腸がんを判断することはできません。しかし、腸内環境の乱れや消化器系の疾患が隠れている可能性があるため、放置は禁物です。
本記事では以下の内容について詳しく解説しています。
- おならの変化と大腸がんとの関係性
- おならが変化する原因となる代表的な疾患
- 食生活や生活習慣が与える影響と対処法
- 大腸がんに気づくきっかけとなる代表的な症状
- 大腸がんを早期発見するための具体的な行動と検査方法
日常のささいな変化にも目を向けることが、病気の早期発見と予防の第一歩になります。
おならは大腸がんの初期症状とはいえない

大腸がんは初期症状を自覚するケースがほとんどないため、おならで大腸がんの有無は判断できません。
しかし、大腸がんが進行するとおならの頻度やにおいが変化する可能性があります。
病変によって便の通過が妨害されると消化が滞り、ガスが増えるためです。
また、がんの代謝産物の影響や腸内フローラの変化によっておならのにおいがきつくなる場合もあります。
おならの変化だけで大腸がんかどうかを判断することはできませんが、おならに変化があるということは、なんらかの異常のサインとも考えられます。
そのほかにも、便秘・下痢などの便の変化や持続的な腹痛などの気になる症状がある場合は、医療機関を受診するのがよいでしょう。
おならが変化する原因となる疾患
おならが変化した場合、以下の疾患が原因の可能性があります。
- 潰瘍性大腸炎
- 過敏性腸症候群
- クローン病
- 胆汁酸吸収不良
腸の働きに影響を及ぼしたり、炎症を引き起こしたりする疾患があるとおならが増えたり、においが変化したりするケースがあります。
これらの疾患は腸のぜん動運動を妨げる原因になり、腸内にガスが増加することでおならの回数が増える可能性があります。
とはいえ、おならは食べるものや生活習慣の影響を受けて変化する場合もあるため、一時的に増えたり臭くなったりしてもすぐ元に戻るのであればあまり心配ありません。
長期間にわたっておならの変化がみられる場合や、他に気になる症状がある場合は医療機関を受診しましょう。
おならが増える・臭くなる要因

おならが増える・臭くなるのには、以下の要因が考えられます。
食生活の乱れ
脂質やタンパク質を多く含む偏った食事はおならが臭くなる可能性があり、食物繊維を過剰摂取した場合はおならの回数が増える可能性があります。
肉や卵などの動物性食品を摂りすぎると、悪玉菌が増加してにおいのあるガスを発生させるため、焼肉やステーキを食べたあとはおならが臭くなりやすいです。
欧米化した食事はおならのにおいがきつくなったり大腸がんのリスクが高まったりする原因であり、間接的に関わっているケースも少なくありません。
また食物繊維は酵素分解によってガスの発生量を増加させることでおならが増える原因になりますが、腸内環境を整える大切な成分です。
摂りすぎに気を付けて適量を意識しましょう。
さらに炭酸飲料やビールなどの炭酸を含む飲み物は、体内で分解される際に二酸化炭素(気体)を発生するためおならが出やすくなることがあります。
ストレスや睡眠不足
ストレスが蓄積した状態や睡眠不足が続くと、自律神経が乱れることでおならが増える場合があります。
自律神経のバランスが崩れると、副交感神経の働きに影響を及ぼすことで胃腸の働きが鈍くなり、消化の機能が低下するためガスが発生しやすくなります。
おならの頻度が増えると、人前で我慢することでさらにストレスが溜まり悪循環に陥るケースがあるため、生活習慣を整えてストレス対策に努めましょう。
消化器系の疾患がある
大腸がんをはじめ、なんらかの消化器系の疾患があるとおならが増えたり臭くなったりする原因になります。
潰瘍性大腸炎やクローン病、過敏性腸症候群などの疾患は腸に炎症を引き起こし、おならの回数やにおいに影響を及ぼす可能性があります。
大腸がんは初期は症状がほぼ見られないものの、進行するとおならが増える場合があります。
空気を飲み込んでいる
身体に異常がなく、心身ともに健康的な生活をしている人でも、空気を飲み込みやすいとおならがよく出るようになります。
空気をたくさん飲んでしまう症状のことを呑気症(どんきしょう)といい、食事を早食いする傾向がある人に多く見られます。
おならのほか、げっぷを頻発する原因でもあるため、よく噛む・ゆっくり食べるのを意識して飲み込む空気の量を減らすことで改善される場合もあるでしょう。
大腸がんに気づくきっかけ?疑われる症状

大腸がんに気付くきっかけになる症状には、以下のものがあります。
なお、大腸がんで症状がみられる場合はすでに進行している可能性が高いため、速やかに医療機関を受診しましょう。
急激な体重減少
必ずしもみられる症状ではありませんが、大腸がんが進行すると、急激に体重が減少する場合があります。
これは、がん細胞が身体から栄養分を奪ったり脂肪やたんぱく質を分解したりするためで、食事制限や運動をしていない場合でもみられる症状です。
食習慣を変えていないのに急激に体重減少がみられる場合は、大腸がんがすでに進行している可能性があります。
3〜4kgほどの原因不明の体重減少がみられる場合は、早めに医療機関にご相談ください。
腹部の張り・痛み
大腸がんがあると、便通異常や便秘によって腹部の張りや痛みが生じるケースがあります。
これは、病変が腸管を塞ぐことによって便の通りが悪くなるためであり、さらに進行すると腹水が溜まる場合もあります。
ただし盲腸や上行結腸などの部位を通過する便は固形化しておらず、腹痛を感じにくく発見が遅れる可能性があるため注意が必要です。
血便・残便感・便が細い
大腸がんでは、便が細い・残便感があるなどの症状のほかに、血便がみられる場合があります。
大腸がんの病変は、形成されるときに栄養を奪うための新しい血管を作り出しますが、この血管は脆弱であるため、便が通過する刺激で出血する可能性があり、それが付着して血便として排出されます。
大腸がんによる排便の減少や残便感は、便が硬くなったり通過が妨げられたりすることで生じ、便秘薬でも解消されません。当てはまる場合は一度内視鏡検査を受けましょう。
めまい・ふらつき
大腸がんが進行すると、めまいやふらつきを引き起こすケースがあります。
病変が作り出した血管からの出血が続くと、貧血になることでこれらの症状につながる恐れがあり、出血が慢性的に続いていることを意味しています。
ただし少しずつ出血するため、気付かぬ間に貧血を引き起こしていたという場合もあり、血液検査で発覚するケースも少なくありません。
便秘と下痢を繰り返す
大腸がんのなかでも、特に上行結腸から直腸にかけての部位に病変が形成された場合は、便秘と下痢を繰り返す症状がみられやすくなります。
腸管が狭くなったり、水分を吸収する機能が低下したりすることが原因で2つの状態の便が繰り返され、腹痛や腹部の張りにつながる可能性もあります。
特に、お腹を壊しやすくこのような症状がよくみられる方は一度検査を受けたほうがよいでしょう。
大腸がんを早期発見するポイント

大腸がんは初期症状がほとんどない疾患であるため、以下のポイントを押さえて出来るだけ早く発見することが大切です。
健康診断や人間ドックを受ける
大腸がんの早期発見には、健康診断や人間ドックが非常に重要です。
大腸がんは症状が出た時点ですでに進行している可能性が高い疾患であるため、早期治療のためには症状がないうちから便潜血検査を受けて発見する必要があります。
大腸がん検診は発症のリスクが高まる40歳頃からの受診が推奨されていますが、まれに若い方でも遺伝性の大腸がんを発症するケースもあります。
家族に大腸がんの既往歴がある場合は、年齢に関わらず検査を受けましょう。
大腸がんが疑われる症状を把握する
大腸がんを症状で早期発見するのは難しいですが、疑われる症状を把握してできるだけ早めに気付くことが大切です。
例えば、便秘と下痢を繰り返す場合は大腸がんが疑われることを知っていれば、なんとなくお腹の調子が悪いときに、楽観視せずに早めに医療機関を受診できます。
気になる症状があれば放置せず、早めに医療機関を受診して詳しい検査を受けることが、大腸がんの早期発見につながるでしょう。
便の状態を観察する
大腸がんがあると便の状態が変化するケースがあるため、普段の便の状態を観察して異変に気付けるようにしましょう。
見た目の変化としては血が混じった便がみられ、排便の変化としては便が細くなる、残便感を感じるなどの異変が生じます。
便は硬すぎず柔らかすぎないものが、いきまずにするっと排出されるのが健康的であるため、変化に気付けるように普段から排便習慣を整えることが大切です。
大腸がんが疑われる場合の検査方法

大腸がんが疑われる場合の検査方法には、以下があります。
|
検査方法 |
| 便潜血検査 |
2日分の便に含まれる血液を調べる |
| 大腸内視鏡検査
(大腸カメラ) |
肛門から内視鏡を挿入し、大腸粘膜を観察する |
| 大腸CT検査 |
炭酸ガスで大腸を膨らませ、CT撮影によって病変を確認する |
| 腫瘍マーカー |
血液を採取して、腫瘍マーカーの量を測定する |
| PET-CT検査 |
薬剤を体内に投入して、ブドウ糖代謝の機能の変化を確認する |
大腸がんの検査では、まず初めに便潜血検査が行われ、陽性だった場合に内視鏡検査や大腸CT検査などの精密検査を行います。
ただし出血を伴わない大腸がんの場合、便潜血検査が陰性になるケースもあるため、内視鏡検査を定期的に受けることが推奨されます。
大腸内視鏡(大腸カメラ)検査では、病変の場所・範囲・大きさを直接確認でき、必要に応じて組織の一部を採取したり、病変を切除したりすることが可能です。
大腸CT検査やPET-CT検査は、大腸がん以外のがんや疾患の発見にも有効で、身体への負担も少ないのが特徴です。
さらにPET-CT検査は、がん組織の活動状態を確認でき、1cmほどの小さな病変の発見にも適しています。
腫瘍マーカーは早期大腸がんの場合は異常がみられないケースが多いため、他の検査と組み合わせて総合的に判断する場合に行われます。
まとめ
おならは大腸がんの判断材料としては不十分な症状ですが、大腸がんが原因で変化する可能性があり、腸に異常をきたす疾患が潜んでいることも考えられます。
おならが増えたり臭くなったりするとストレスにもなるため、気になる場合は一度医療機関を受診しましょう。
えさか駅前にしごりおなかとおしりのクリニックでは、大腸がんをはじめとしたおなか・おしりのさまざまな疾患に対して専門的な診療を提供いたします。
日常的に起こりやすい症状でも、詳細な検査によって重大な病気を早期発見するきっかけになるため、気になる症状がある方はお早めにご相談ください。