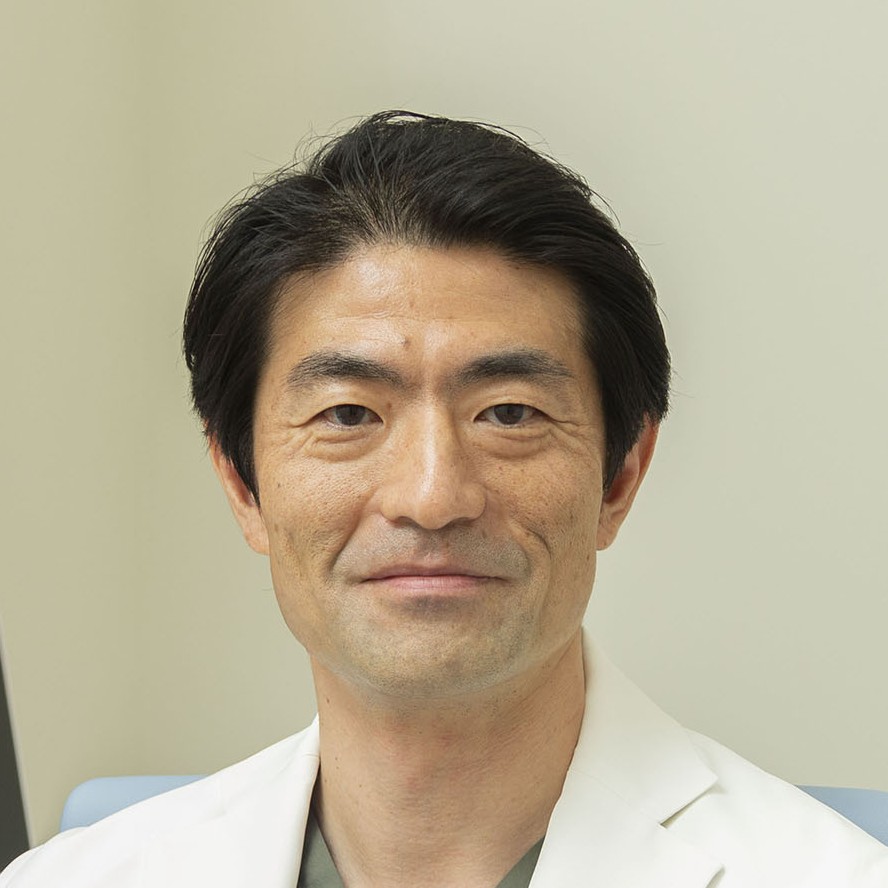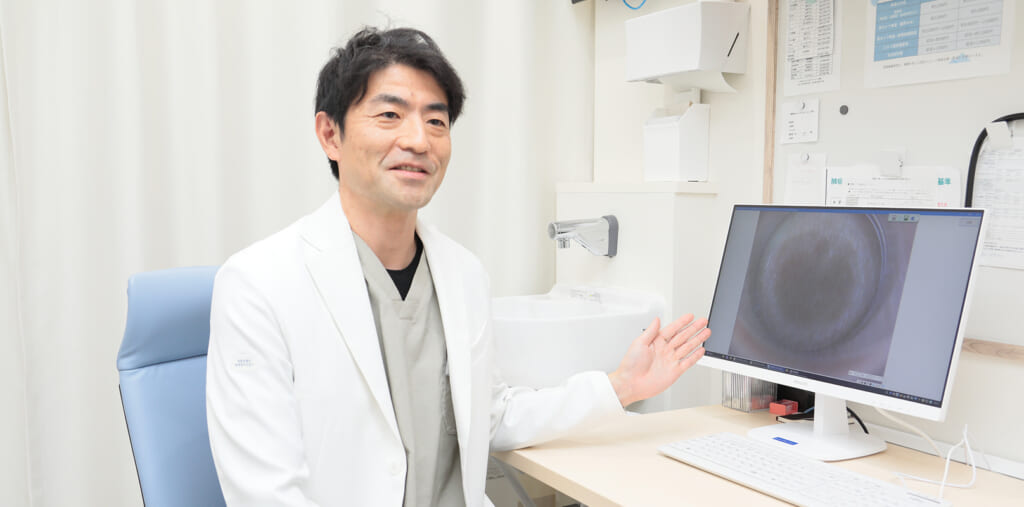痔と大腸がんは、どちらも「出血」や「排便異常」といった共通する症状があり、自己判断で見分けるのが難しい病気です。特に初期の大腸がんでは、痔と似たような血便が現れるため、誤認しやすく注意が必要です。
実際に、以下のような違いがあります。
- 痔の出血は、排便時にティッシュや便器に付く鮮血が多く、痛みを伴うことが多い
- 大腸がんの出血は、暗赤色便や潜血便の形で現れ、痛みを伴わないケースが多い
- 痔の症状には、肛門周囲の痛みや腫れ、いぼ状のふくらみなどがあり、比較的わかりやすい
- 大腸がんの症状には、便が細くなる・残便感・慢性的な貧血・腹部膨満感・下痢と便秘の繰り返しなど、全身に及ぶ異変がみられる
特に出血のタイプが似ているため、「痔だと思って様子を見る」ことで発見が遅れ、進行してしまうリスクがあります。自己判断に頼らず、便潜血検査や大腸内視鏡検査による早期発見が重要です。
本記事では、大腸がんと痔の出血や症状の違いを中心に解説します。血便の種類と原因疾患の見分け方、痔との違いや他の病気の特徴を紹介しながら、大腸がんを見逃さないための検査法と受診の目安についてもわかりやすく説明します。
【早見表】痔と大腸がんの出血・症状の違い

痔と大腸がんについて、出血の種類・場所、症状の違いを表にまとめました。
出血を伴う便の種類ごとに、大腸以外のがんも含めています。
あくまで一例ですが、参考にしてください。
| 出血の種類 | 出血場所 | 症状 | がん・ポリープ | 痔 | それ以外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出血の程度はさまざま | 肛門 | なし | 内痔核 急性裂肛 慢性裂肛 |
||
| 潜血便(微量の血液が混じった便) | 直腸 肛門 |
なし | 大腸(直腸)がん 大腸ポリープ |
内外痔核 | 潰瘍性大腸炎 直腸潰瘍 |
| 暗赤色便(血液が酸化し位赤色に変色した便) | 大腸 | なし~ 貧血 便通異常 腹部膨満感 |
大腸(結腸)がん 大腸ポリープ |
||
| なし~ 発熱 腹痛 |
虚血性腸炎 感染性腸炎 潰瘍性大腸炎 クローン病 |
||||
| なし~ 腹痛 |
大腸憩室出血 | ||||
| 小腸 | なし~ 腹痛 貧血 |
小腸潰瘍
メッケル憩室出血 |
|||
| 粘血便(ゼリー状の分泌物と血液が混ざった便) | 大腸 | 下痢
渋り腹 |
潰瘍性大腸炎 | ||
| 黒色便 (下血) |
胃 | なし~ 腹痛 貧血 |
胃がん 胃ポリープ |
胃潰瘍 | |
| 十二指腸 | なし~ 腹痛 貧血 |
がん ポリープ |
十二指腸潰瘍 | ||
| 食道 | なし~ 心窩部痛 食道閉塞感 貧血 |
食道がん | 逆流性食道炎 食道静脈瘤破裂 |
下血とは、消化管全体のいずれかで出血が起こり、血液が便として排出される状態を指します。特に黒色便(タール便)は上部消化管からの出血を示します。
一方、血便とは下血の中でも主に下部消化管(大腸)からの出血のみを表すものです。
その中で、痔の出血はトイレットペーパーにつく程度と潜血便のみで、その他は痔以外での病気での血便の可能性があります。
痔以外の病気でも自覚症状がない場合があるため、出血の種類・大小に関わらず専門のクリニックを受診しましょう。
特に、大腸がんの血便の種類が痔同様の潜血便のため、出血を発見した場合に様子見をしてはいけないことが分かります。
大腸がんの症状と出血の特徴

初期段階では自覚症状がほとんどない大腸がんは、以下のような経過で進行していきます。
- 血が混じった暗赤色便、または便の表面に血が付くようになる
- 慢性的に出血するようになり、貧血の症状が出てくる
- 便が細くなる・残便感がある・お腹が張る
- 腸閉塞を引き起こし、便が出なくなる・腹痛や嘔吐などが起こる
大腸がんの症状の中で頻度が高いのは、便に血が混じる・付着するという症状です。
大腸がんはがんができる位置で『直腸がん』と『結腸がん』に分けられます。
直腸がんは肛門に近いため潜血便が見られる頻度が高く、結腸がんは大腸奥の出血で排便まで時間があるため暗赤色便の頻度が高いです。
痔でも良性の病気でも出血は起こりますが、自己判断して様子を見たりせず、早めにクリニックを受診しましょう。
痔の症状と出血の特徴

痔にはいくつか種類がありますが、出血を伴う痔にはいぼ痔と切れ痔があります。
それぞれについて紹介するため、大腸がんと比べてみましょう。
いぼ痔(痔核)
排便時に肛門に過度な負担がかかったり、便秘や下痢を繰り返したりすることで起こる痔です。いぼの他にうっ血や腫れも起こり、排便時に出血するようになります。
歯状線(肛門と直腸の境目で外からは見えない)を基準に内側にできれば『内痔核』、外側にできれば『外痔核』です。それぞれの特徴は以下です。
- 内痔核……出血はティッシュにつく程度。重症になると排便の度に出血・量も多くなる
- 一般的にいぼ痔といえば内痔核
- 通常は痛くない
- デスクワークなど長時間の同じ姿勢で座っていると起こりやすい
- 患者数が多い
- 外痔核……鮮血便
- 便秘やスポーツでのいきみなどで起こる
- 歯状線がうっ血・内出血を起こし、中に血栓ができて膨らんだもの
- 強い痛みがある
出血の量については多いときと少ないときの差が激しい傾向があり、多いときは便器が血で染まるほど大量に出血します。
切れ痔(裂肛)
歯状線より下の部分の肛門上皮が裂けて傷ができた痔で、肛門の後方に起こりやすいです。
便秘で太く硬くなった便の排泄や、慢性の下痢で皮膚が炎症が生じ裂けやすくなることで起こります。
排便の度に強い痛みがあり、潜血便が特徴ですが、大量に出血することはあまりありません。
痛みのため排便を先延ばしにしがちで、さらに便が硬くなってしまう悪循環が起こりやすい痔です。
痔以外の症状と出血の特徴

大腸がんと痔以外で出血する病気は他にもあります。
以下は、出血の症状を伴う大腸がん以外の病気です。
- 大腸ポリープ……成長するとがん化することもある
- 潰瘍性大腸炎……腹痛や血便があるため直腸がんに似ている
- クローン病……腹痛や下痢・発熱が主な症状
- 虚血性腸炎……左下腹部痛が突然起こる。その後下痢や下血が起こる
- 大腸憩室症……腹痛・下痢・便秘が主症状。大腸壁に袋状の凹みができる
これらの病気は下痢や便秘・腹痛など、日常的に起こる症状であるため見過ごされがちです。
しかしいずれも様子見していていい病気ではないため、速やかな受診が大切です。
大腸がんの検査

出血のある便を痔と決めつけることは、大腸がんの発見を遅らせる可能性があります。
大腸がんは早期発見・早期治療で完治が期待できるがんです。
ここでは、大腸がんを発見する検査について紹介します。
便潜血反応検査
便潜血反応検査は、便に血が混じっていないかを見る検査で、免疫反応を利用して目に見えないレベルの血が便に混じっていないかを調べます。
日本では、自覚症状のない早期の大腸がんを発見するため、40歳以上を対象とした便潜血反応検査が市区町村で実施されています。
検診でよく行われる検査で、便の一部を二日間に分けて採取するだけの簡単な検査ですが、陽性が出た場合は精密検査の対象です。
便潜血反応検査は、大腸がんの早期発見に有用ですが、偽陽性や偽陰性もあるため、毎年の受診や必要に応じて大腸内視鏡検査の併用が推奨されます。
CT・MRI・PET-CT検査
撮影によって大腸を発見する検査です。
- CT検査……X線による断層写真
- CTC検査……炭酸ガスで大腸を膨らませて撮影するCT検査
- MRI検査……磁場と電波による断層撮影
- PET-CT検査……検査薬とX線を併用して撮影する。初期がん発見率が高め
さまざまな検査と併用して行うことで、大腸がん発見の精度の向上が期待できます。
指診
指診は肛門から人差し指を差し入れて直腸を調べます。
直腸がんの70%は人間の指が届く直腸の下部にあるため、発見できる確率が高いです。
大腸内視鏡検査
大腸内視鏡検査(大腸カメラ検査)は信頼できる大腸がんの検査法で、大腸内を直接観察できる唯一の方法です。
肛門から内視鏡(細いカメラ)を挿入して、直腸から盲腸までの大腸全体を詳しく観察できます。
検査中にポリープを発見した場合、その場で切除も可能です(内視鏡下ポリープ切除術)。
苦痛を伴う検査と考える方もいますが、検査前には浣腸ではなく経口の腸管洗浄剤で大腸内をきれいにし、細いカメラを使用します。
鎮静剤を用いてリラックスするなど、苦痛が軽減される検査が主流になっています。
注腸バリウム造影検査
肛門からバリウムと空気を入れて大腸内をX線で撮影する、精度の高い検査です。
大腸の壁に発生した病変やがんの位置・大きさを含む形容などの判断が可能です。
検査時間は10分程度で痛みはありません。
ただし、高齢の女性・婦人科手術経験のある女性・便秘のある方は受けられないことがあります。
大腸がんを早期発見するには

大腸がんを早期発見するには、まずは検診や人間ドッグによる便潜血検査を受けるのが有効です。
また、以下の場合は大腸内視鏡検査をぜひ受けましょう。
- 便潜血検査で一度でも陽性となった場合
- 検診で要検査判定が出た場合
- 何かしらの症状があって気になる場合
- 特に何も症状がない場合でも40歳を過ぎたら
何も症状がない場合に大腸内視鏡を受けると健康保険適用外ですが、検査中に病変の発見やポリープ切除があった場合は保険適用です。
大腸内視鏡検査を受けることで、大腸がんを含め以下のような病気も発見できます。
- 大腸がん
- 肛門管がん
- 大腸ポリープ
- 潰瘍性大腸炎
- 大腸憩室症
肛門管がんは痔と紛らわしいがんで発生率が低いですが、痔瘻を治療せずに長く放置するとまれに発生するがんです。
自己判断で放置してしまい見逃しがちになる病気を早期に発見するためには、検査による積極的なアプローチが必要です。
まとめ
何か体の不調があった場合、そのうち治ることを期待したり、体質だと思ったりすることで「様子を見る」という行動を取る人は多いです。
しかしその行動が、早く発見すれば治る病気を治らないものにしてしまう場合があります。
日本人の死亡原因の第1位はがんで、そのうち大腸がんの罹患率は男女ともに2位、死亡数は男性が2位・女性が3位という結果です。
えさか駅前にしごりおなかとおしりのクリニックでは、早期発見することで完治が期待できる大腸がんを発見するための最新の内視鏡システムで、専門医が質の高い検査を提供しています。また痔核(いぼ痔)、痔瘻(あな痔)、裂肛(切れ痔)や肛門ポリープなどの肛門疾患に対し、肛門外科の日帰り手術を行っています。下血、出血に対して、大腸内視鏡検査のみならず肛門疾患に対する日帰り手術までお悩みに対し完結すべく診療を行っております。
忙しい中でも早く検査が受けられるよう、土曜日も会社帰りのアフターファイブも機会を用意しております。
最近おなかの調子が悪い・痔が気になっているという方は、お気軽にお問い合わせ下さい。