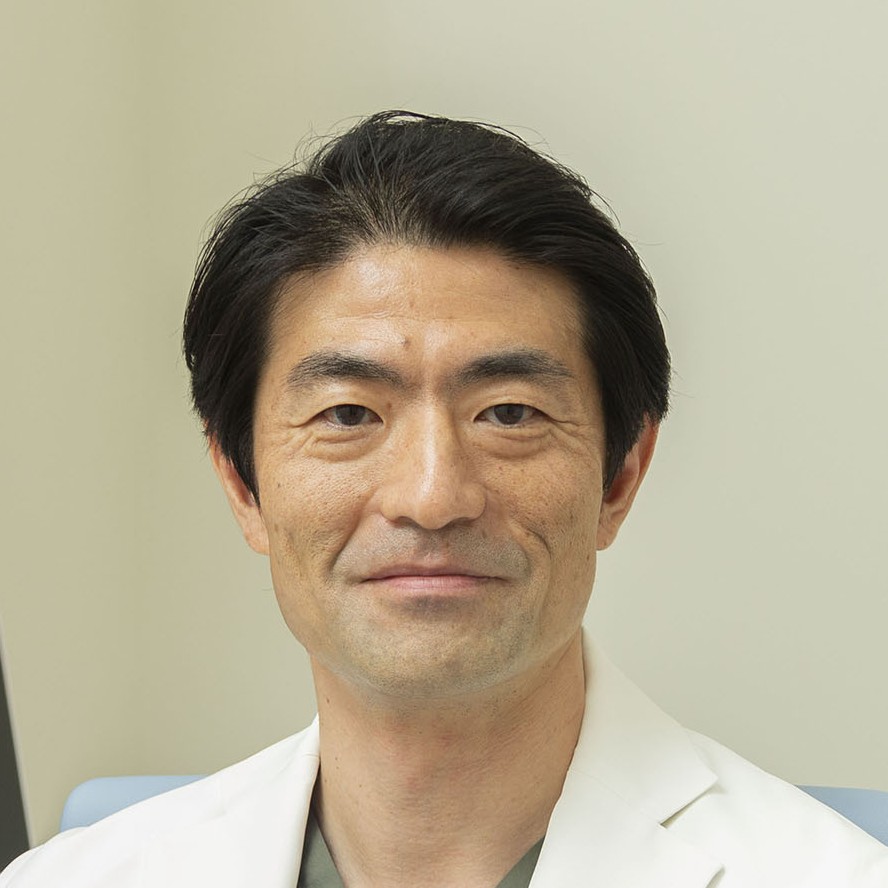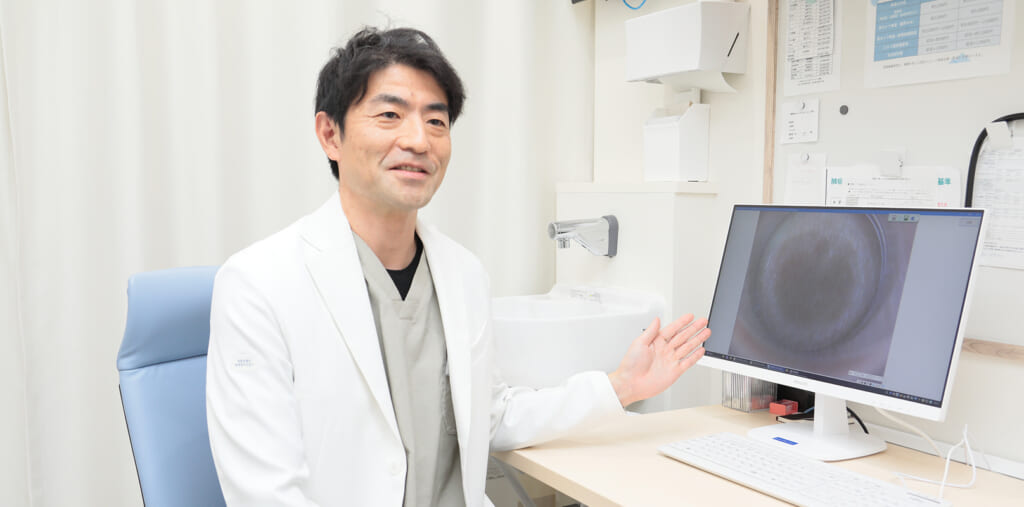「食欲もあり体調も悪くないのに、なぜか下痢だけが続いている」そんな悩みを抱える方は少なくありません。元気なのに下痢が続く場合、一時的な不調ではなく、慢性疾患や消化器系の異常が関係している可能性があります。
本記事でわかること
- 下痢のタイプ(急性/慢性)とそれぞれの主な原因
- 続く下痢からわかる可能性のある病気と特徴
- 自宅でできる下痢の対処法と避けるべき食事
- 医療機関で行われる主な検査と治療の選択肢
一見深刻に見えない症状でも、正しい理解と対処が将来の健康を左右します。まずは下痢のメカニズムを知ることから始めましょう。
元気なのに下痢が続く?2種類の原因

下痢は『急性下痢』と『慢性下痢』の2種類に分けられます。
急性下痢と慢性下痢はそれぞれ原因や対処方法が異なるため、元気なのに下痢が続く場合には、どちらに当てはまるか見極めることが大切です。
ここではそれぞれの原因について解説します。
急性下痢
急性下痢とは、突発的に始まり2週間以内に治まる下痢のことです。
主な原因として、以下のようなものが挙げられます。
- ウイルスや細菌による感染症
- 食中毒
- 食べ過ぎ・飲みすぎ
- 食物アレルギー
- 薬の副作用
また急性下痢は発症メカニズムによってさらに以下の2種類に分けられます。
| 急性下痢の種類 |
発症メカニズム |
主な原因
|
| 浸透圧性下痢 |
水分を引き寄せる力が高い飲食物によって、腸の水分の吸収が妨げられることで起こる下痢 |
過剰なアルコール摂取、キシリトール、ソルビトール、マンニトール、人工甘味料、一部の果物や豆類、濃度の高いジュース、MCTオイル、酸化マグネシウムなどの下剤、牛乳(乳糖不耐症の人の場合) |
| 分泌性下痢 |
腸管から水分や電解質が過剰に分泌されることによって起こる下痢 |
食中毒や感染症、下剤の副作用、食物アレルギーなど |
慢性下痢
慢性下痢とは、1か月以上下痢が続いている状態です。
主な原因として、以下が挙げられます。
- 腸の病気
- アレルギー
- 薬の副作用
- 慢性的なストレスや不規則な生活習慣
また慢性下痢は発症メカニズムによって以下の2種類に分けられます。
| 慢性下痢の種類 |
発症メカニズム |
主な原因 |
| ぜん動運動性下痢 |
何らかの原因で大腸の運動が過剰になることで、水分が吸収されないまま便として排出されてしまうことで起こる下痢 |
ストレスや冷えによる自律神経の乱れ、過度なアルコール摂取、不規則な生活など |
| 滲出性下痢 |
大腸の粘膜にできた潰瘍や炎症などにより、水分の吸収能力が低下することで起こる下痢 |
潰瘍性大腸炎、クローン病、腸管出血性大腸菌、がんなど |
下痢の症状

そもそも、下痢とは水分を多く含んだ軟らかい便や水のような便が通常よりも頻繁に排出される状態を指します。
健康な便の水分量は60〜70%程度ですが、これが80〜90%に達すると『泥状便』、90%を超えると『水様便』となり、いずれも下痢の状態とみなされます。
また排便の回数が増えることも特徴のひとつです。
1日に3回以上の排便が続いたり、急な便意を繰り返す場合は下痢と判断されます。
下痢が数日で治まる場合は経過観察で済むことが多いですが、1週間以上続く、血便が混じる、発熱や激しい腹痛を伴うなどの症状がある場合は早めに消化器内科を受診しましょう。
下痢になったときの対処方法

下痢になったときの対処方法として、以下の4つが挙げられます。
- 水分を十分に摂取する
- 消化の良い食事を選ぶ
- 下痢になりやすい食品を避ける
- 刺激の強い食品を控える
それぞれ詳しく解説します。
水分を十分に摂取する
激しい下痢の場合は脱水症状を引き起こす恐れがあるため、水分を十分に摂取することが大切です。
冷たい飲み物は胃腸を刺激しやすいため、ぬるめの白湯や薄い番茶、麦茶、経口補水液などを少量ずつこまめに飲むようにしましょう。
水分といっても牛乳は腸への刺激が強いため、避けるのが無難です。
また嘔吐と下痢によって十分に水分補給ができない場合には、早めに医療機関を受診しましょう。
消化の良い食事を選ぶ
無理のない範囲で消化の良い食事を摂るようにしましょう。
胃腸を休ませることが目的のため、油分や食物繊維の多い食品は避け、調理もなるべくシンプルにすることが大切です。
下痢になったときにおすすめの食事としては、以下が挙げられます。
- おかゆ
- 煮込みうどん
- 野菜スープ
- すりおろしたリンゴ
- バナナ
- 卵
- 豆腐
- 鶏のささみ
- 白身魚など
いずれも体への負担が少なく、栄養も摂りやすい食品です。
下痢になりやすい食品を避ける
下痢のときは、胃腸に負担のかかる食品や下痢になりやすい食品は避けましょう。
具体的には以下のような食品が挙げられます。
- 脂肪分の多い肉類
- 揚げ物
- ラーメン
- スナック菓子
- 海藻類
- 玄米
- 発酵しやすい野菜(キャベツやさつまいもなど)
このほか、カフェイン飲料や炭酸飲料、お酒なども控えるのが無難です。
刺激の強い食品を控える
下痢のときは胃腸が敏感になっているため、刺激の強い食品は控えましょう。
具体的には以下のような食品が挙げられます。
- 香辛料
- カフェイン飲料
- アルコール
- 柑橘類
- 濃い味付けの料理
- 酸味の強い食品
これらの食品を下痢のときに摂取すると、症状が悪化する恐れがあります。
症状が治まっても、数日は控えると安心です。
下痢が続く場合に考えられる病気

下痢が続く場合に考えられる病気として、以下の5つが挙げられます。
- 感染性胃腸炎
- 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)
- 過敏性腸症候群
- 大腸がん
- 慢性膵炎
ここでは上記5つの病気についてそれぞれ解説します。
感染性胃腸炎
感染性胃腸炎は、細菌やウイルスが腸に感染することで発症する病気です。
主な原因としては、ノロウイルス、ロタウイルス、カンピロバクター、病原性大腸菌(O-157など)が挙げられます。
感染源となる食品や水、または汚染された手指を介して口に入ることで発症します。
激しい下痢・嘔吐・腹痛・発熱などが主な症状です。
特に水様性の下痢が繰り返される場合、脱水のリスクが高まるため注意が必要です。
市販の下痢止めは、体外に出すべき病原体の排出を妨げて症状を悪化させる可能性があるため、使用するのは避けましょう。
症状が強い場合は医療機関を受診し、適切な治療を受けることが大切です。
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)
炎症性腸疾患は、腸に慢性的な炎症が起こる原因不明の疾患で、代表的なものに『潰瘍性大腸炎』と『クローン病』があります。
いずれも厚生労働省により難病指定されている病気です。
潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜に炎症や潰瘍ができ、血便や下痢、腹痛が続きます。
クローン病は消化管全体に炎症が起こる可能性があり、小腸から肛門まであらゆる部位に症状が見られます。
いずれも再発と寛解を繰り返すのが特徴で、放置すると腸閉塞や大腸がんなどの合併症を引き起こすこともある病気です。
適切な治療を受けることで、良好な状態を長く維持できます。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群は、腸に明らかな炎症や腫瘍などの異常が見られないにもかかわらず、腹痛や下痢・便秘といった症状が長期的に続く機能性疾患です。
ストレスや緊張、不規則な生活が症状の悪化を引き起こす要因とされており、比較的若年層にも多い疾患です。
過敏性腸症候群には『下痢型』『便秘型』『交代型』(下痢と便秘を交互に繰り返す)があり、特に下痢型では突然の便意とともに1日に何度も水様便を排出するケースもあります。
日常生活に支障をきたすことも多く、生活習慣の見直しやストレス対策が治療の基本となります。
症状が続く場合は、消化器内科の受診を検討しましょう。
大腸がん
大腸がんは初期には自覚症状がほとんどなく、進行してから下痢や便秘、血便、便が細くなるなどの症状が現れます。
こうした症状は一見軽度に見えるため、つい見過ごされがちですが、50歳以上で下痢が続く場合は特に注意が必要です。
がんが進行すると、腸の内腔が狭くなり便の通過が妨げられるため、便秘と下痢を繰り返すようになります。
早期発見のためには、便潜血検査や大腸内視鏡検査が有効です。
大腸がんはポリープの段階で発見すれば、日帰りの内視鏡手術で治療できるケースも多くあります。
将来のリスクを軽減するためには、些細な症状でも検査を受けておくことが大切です。
下痢の検査方法

下痢が長引く場合や原因がはっきりしないときは、適切な検査によって原因を突き止めることが大切です。
まず行われるのが問診で、便の状態(形状・色・におい・回数)、発症時期、併発する症状(発熱・腹痛・血便など)、食生活の内容、服薬歴、既往歴などを詳しく確認します。
問診によって感染性か機能性か、急性か慢性かの判断を行い、必要な検査を選択していきます。
下痢の主な検査方法は以下の通りです。
| 血液検査 |
炎症の有無や脱水症状、栄養状態などを評価するために行う検査 |
| 腹部レントゲン検査 |
腸のガスのたまり具合や閉塞の有無などを確認するために行う検査。腸閉塞や腸の異常な動きなどが疑われる場合に有効 |
| 便潜血検査 |
便に肉眼では見えない微量の血液が混ざっていないかを調べる検査。大腸がんやポリープ、腸の炎症などの早期発見に役立つ |
| 腹部エコー検査 |
超音波で肝臓、膵臓、腎臓、胆のうなど内臓の状態を確認する検査。腸管のむくみや腹水など、下痢の原因となる疾患の有無も調べられる |
| 大腸カメラ検査 |
内視鏡を使って大腸の粘膜を直接観察する検査。ポリープやがん、潰瘍性大腸炎などの診断に有効で、必要に応じて組織検査も行う |
下痢の検査は問診と組み合わせて複数の方法で総合的に判断されるため、自己判断せず、医師の指示に従って検査を受けることが大切です。
下痢の治療方法

下痢の治療は、その原因によって大きく異なります。
単なる食べ過ぎや一時的なストレスによるものなど、急性の下痢であれば自然に治まるケースも多いため、特別な治療は不要な場合もあります。
しかし感染症や慢性的な疾患、重度の症状が伴う場合には、適切な治療が必要です。
急性下痢と慢性下痢の主な原因、治療の基本方針、具体的な対処法を以下にまとめました。
| 下痢のタイプ |
主な原因 |
治療の基本方針 |
具体的な対処法 |
| 急性下痢 |
ウイルス・細菌感染、食べすぎ、ストレスなど |
水分補給・整腸剤・安静(原則として下痢止めは使わない) |
経口補水液・スポーツドリンク・麦茶などでこまめな水分補給、消化の良い食事(おかゆ、うどん) |
| 慢性下痢 |
過敏性腸症候群、炎症性腸疾患、大腸がんなど |
原因疾患の治療・食事や生活習慣の見直し |
脂肪・刺激物を避ける、栄養バランスの取れた食事、原因疾患に対する治療 |
急性下痢の場合、まずは脱水を防ぐためのこまめな水分補給が最優先です。経口補水液や麦茶、薄めのスポーツドリンクなどが適しています。また、症状が落ち着いた後にはおかゆやうどんなどの消化に優しい食事を少量ずつ摂るようにします。
注意点として、感染性の急性下痢では、下痢止めの使用は推奨されていません。病原体を体外に排出できず、症状が悪化するおそれがあるためです。
一方で慢性下痢の場合は、背景に病気が潜んでいる可能性があるため、原因疾患の特定とその治療が第一優先となります。
加えて、脂肪分の多い食事や香辛料、アルコール、カフェインなど刺激物を控える、生活リズムを安定させるといった日常的な管理が長期的な改善に役立ちます。
まとめ
下痢が続く場合の原因は、一過性の体調不良から慢性疾患までさまざまなものが考えられます。
まずは生活習慣を見直し、必要に応じて医療機関で検査を受けましょう。
血液検査や便潜血検査、大腸カメラ検査などを受けることで正確な診断ができ、適切な治療につながります。
えさか駅前にしごりおなかとおしりのクリニックでは、お腹とお尻のさまざまな病気の診断・治療を行っています。
女性医師による内視鏡検査にも対応しているため、大腸カメラ検査が恥ずかしいと感じる女性の方も、ぜひ気軽にご相談ください。