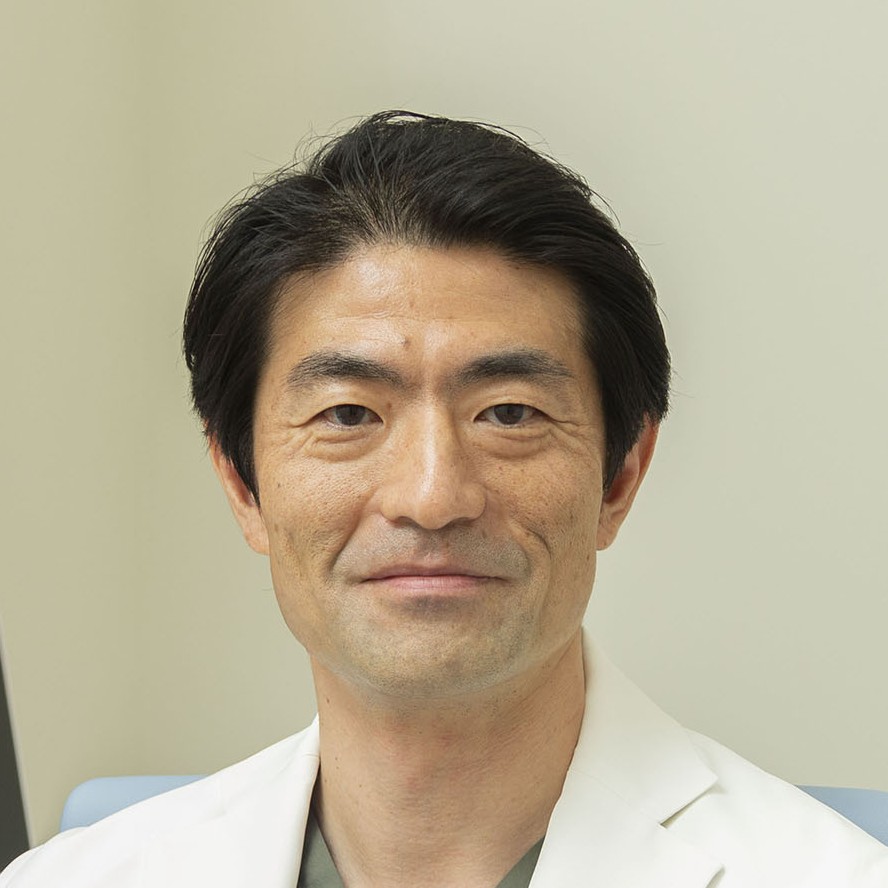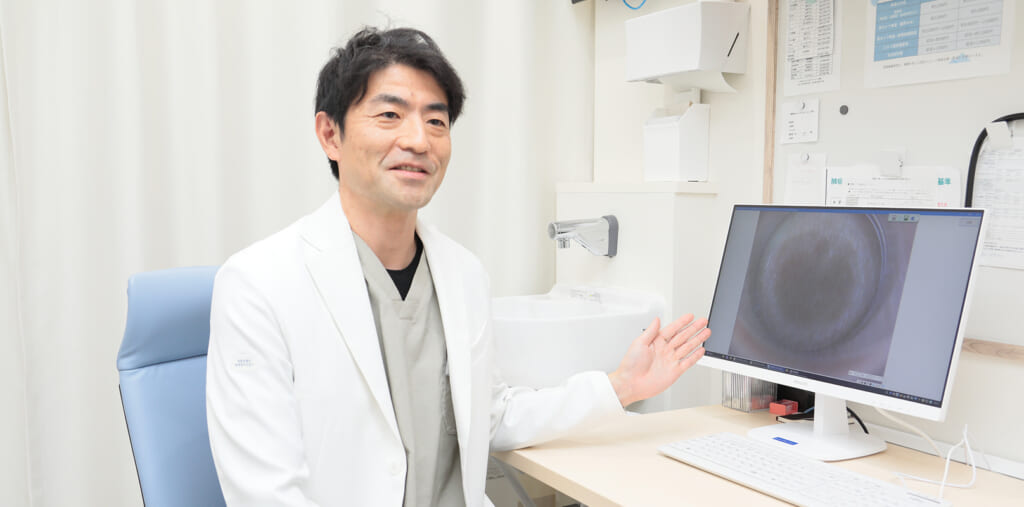静かな会議中や授業中などに「お腹が鳴ってしまった」という経験をしたことがある方は多いのではないでしょうか。お腹が鳴る現象は、誰にでも起こる生理的なもので、基本的には病気ではありません。
しかし頻繁に鳴ったり、音が大きすぎたりすると気になってしまい、日常生活に支障をきたすこともあります。
この記事では、お腹がゴロゴロ・ギュルギュル鳴る理由について詳しく解説します。注意すべきお腹の音やお腹が鳴るときに考えられる病気、具体的な対策・予防方法などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
お腹がゴロゴロ・ギュルギュル鳴る理由

お腹がゴロゴロ・ギュルギュル鳴る理由として、主に以下の5つが挙げられます。
- 食べ物を消化している
- 空腹
- 腸内にガスが溜まっている
- 生理・妊娠
- 精神的なストレスや生活習慣の乱れ
それぞれ解説します。
食べ物を消化している
食後にお腹が鳴るのは、胃や腸が食べ物を消化しようとして活発に動いているためです。
消化管が食べ物や飲み込んだ空気、消化液を腸内に送り出す際に、ゴロゴロ・ギュルギュルと音が鳴ります。
特に炭酸飲料やガスが発生しやすい食品(豆類、キャベツ、イモ類など)を食べた場合は、音が大きくなることもあります。
また早食いや噛まずに飲み込むなどで空気が多く混入し、腸内でガスが発生しやすくなるのも一因です。
こうした音は消化が正常に行われている証拠でもあるため、基本的には問題ありません。
空腹
空腹時にお腹が鳴るのは、胃や腸が次の食事に備えて動き始めるためです。
体は食べ物が入っていなくても、残っている消化物や空気、消化液を移動させようとして『空腹時収縮』という動きを始めます。
この際に発生する摩擦音やガスの移動音が「グーッ」という音になるのです。
さらに、空腹を知らせるホルモン『グレリン』の働きによって腸の運動が活発になり、音が目立ちやすくなります。
空腹時の音は一時的なもので、規則正しく食事をとれば抑えられることが多いです。
腸内にガスが溜まっている
腸内にガスが溜まると、それが移動する際に「ボコボコ」「グルグル」といった音が発生します。
特に食物繊維が多い食品や、炭酸飲料、豆類、乳製品などはガスを発生させやすいとされています。
腸の狭い部分をガスが通ると大きな音が鳴ることがありますが、基本的には健康に問題ありません。
ガスが溜まりやすい人はお腹の音が気になりやすくなりますが、腸の動きによる正常な現象です。
生理・妊娠
女性の場合、生理や妊娠によりホルモンバランスが変化し、腸の動きに影響が出ることがあります。
生理中はプロスタグランジンというホルモンの影響で子宮だけでなく腸も刺激され、腸が活発に動いたり、逆に鈍くなったりすることでお腹が鳴りやすくなるのです。
妊娠初期には腸の運動が緩やかになり、ガスが溜まりやすくなるため、ゴロゴロ音が目立つことがあるでしょう。
いずれも一時的な現象のため、過度に心配する必要はありませんが、苦痛を感じる場合は医師に相談してみるのがおすすめです。
精神的なストレスや生活習慣の乱れ
ストレスや生活習慣の乱れもお腹が鳴る原因となります。
自律神経は腸の動きをコントロールしていますが、強い緊張や不安を感じるとこのバランスが崩れ、腸が過敏に反応してしまいます。
腸のぜん動運動が不規則になったり、ガスが過剰に発生したりすることで、お腹がグルグル鳴りやすくなるのです。
また睡眠不足や不規則な食生活、運動不足も腸内環境に悪影響を与え、音が目立つ要因となります。
このような原因がある場合は、ストレスケアや生活リズムの見直しが大切です。
お腹が鳴りやすい人の特徴

お腹がゴロゴロ・ギュルギュル鳴るのは誰にでも起こりうる現象ですが、特に鳴りやすい人の特徴は以下の通りです。
- 長時間座って仕事や生活をしている人
- 冷え性の人
- 早食いの癖がある人
- 脂っこいものばかり食べている人
- アルコールを過剰摂取している人
- 香辛料などの刺激物を好んで食べる人
- 運動不足の人
- 便秘気味の人
- ストレスを感じやすい人
上記に当てはまる人はお腹が鳴りやすい傾向にあるため、日々の生活で改善できる点がないか見直してみましょう。
適度な運動やバランスの良い食事、リラックスできる時間の確保などを意識することで、改善できる可能性があります。
お腹の音に関して注意すべき症状

お腹の音に関して注意すべき症状として、以下の5つが挙げられます。
- 持続的な腹痛
- 腹部の腫れ・膨満感
- 吐き気・嘔吐
- 便の異常
- その他の症状
ここでは上記5つの症状についてそれぞれ解説します。
持続的な腹痛
お腹の音に加えて持続的な腹痛がある場合、腸や胃の炎症、感染症、腸閉塞などの病気が疑われます。
特に痛みが強かったり、繰り返し起こったりする場合には注意が必要です。
過敏性腸症候群のように慢性的な痛みを引き起こす病気もあれば、盲腸炎や消化管穿孔のように緊急性のある病気もあります。
また発熱や吐き気、便の異常などを伴う場合は、感染性胃腸炎などの可能性も考えられます。
市販薬で症状が緩和しない場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。
腹部の腫れ・膨満感
お腹の音とともに腹部が張って苦しい、膨らんだように感じる場合には、腸内にガスや内容物が過剰に溜まっている可能性があります。
これは便秘や過敏性腸症候群でもよくみられる症状です。
一方で、腸閉塞や腫瘍によって内容物の通過が妨げられているケースもあるため、注意が必要です。
膨満感が数日続き、食事が取れない、痛みがあるといった症状を伴う場合は、医師の診察を受けましょう。
吐き気・嘔吐
お腹の音に加えて吐き気や嘔吐が見られるときは、胃腸炎や腸閉塞などが原因である可能性があります。
| 原因となる病気 | 特徴 |
|---|---|
| 胃腸炎 | ウイルスや細菌による感染が原因で起こる病気で、腸の炎症によってお腹の音が目立ったり、吐き気や嘔吐を伴ったりすることがある |
| 腸閉塞 | 腸が詰まりガスが溜まりやすくなることで、お腹の音が強くなったり、腹痛・嘔吐を伴ったりすることがある |
特に嘔吐が繰り返される場合は脱水のリスクもあるため、迅速な対応が必要です。
症状が治まらない、または繰り返す場合は、消化器内科の受診をおすすめします。
便の異常
お腹の音に加えて便の色や形、頻度に異常が見られる場合、腸内に何らかの異常が生じていると考えられます。
例えば黒色便や血便、粘液便は消化管からの出血や炎症の可能性があり、放置すると症状が悪化することもあるため注意が必要です。
便秘や下痢を繰り返す場合は、過敏性腸症候群や腸炎、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)などが原因となることもあります。
便の変化が急に現れた場合には、早めに検査を受けることが大切です。
その他の症状
お腹の音とともに、体重減少や食欲不振、貧血、疲労感、発熱などがみられる場合は、消化器疾患や全身疾患が関与している可能性があります。
例えば胃がんや大腸がんでは初期に目立った症状が出にくいものの、上記のような慢性的な異常が現れることがあります。
また吐血や血便がある場合は緊急性が高いため、すぐに受診が必要です。
普段と異なる体調の変化を感じたら、早めに医療機関を受診するようにしましょう。
お腹が鳴る場合に考えられる病気

お腹が鳴る場合に考えられる病気は、主に以下の5つです。病名と症状・特徴を整理しました。
| 病名 | 主な症状・特徴 |
|---|---|
| 過敏性腸症候群 | 腹痛、下痢・便秘の反復、ストレスや自律神経の乱れが関与 |
| 大腸がん | 血便、便が細くなる、便秘と下痢の繰り返し、体重減少などが進行とともに出現 |
| 腸閉塞 | 激しい腹痛、吐き気、便やガスが出ない、腹部膨満 |
| 急性胃腸炎 | 下痢、嘔吐、発熱、腹痛、吐き気など/感染性が多い |
| 乳糖不耐症 | 牛乳や乳製品摂取後の腹鳴、腹痛、下痢/ラクターゼ酵素の不足が原因 |
お腹の音だけで病気かどうかを判断することは難しいですが、音の変化とともに腹痛・下痢・血便・体重減少などの症状がある場合は、早めに医療機関で検査を受けてください。
お腹が鳴ったときの対策

ここでは、お腹が鳴ったときの具体的な対策を2つ紹介します。
背筋を伸ばす
お腹の音が気になるときは、まず姿勢を正すことを意識してみましょう。
猫背や前かがみの姿勢は腹部を圧迫し、腸の動きを妨げることで音が出やすくなります。背筋を伸ばして座ることで腸が本来の位置に戻り、ぜん動運動がスムーズになりやすくなります。
また、姿勢が整うことで深く落ち着いた呼吸がしやすくなり、緊張もやわらぐため、音の軽減にもつながります。
◯実践の手順
1.足裏をしっかり床につける
2.骨盤を立てて座る
3.背もたれを使わず、自分の筋力で背筋を保つ
少量のジュースやお菓子を摂取する
お腹が鳴る原因のひとつに、空腹時に起こる胃腸の収縮運動(空腹時収縮)があります。この動きによって腸内のガスや液体が移動し、音が発生します。
このようなときは、少量の飲食で胃腸の動きを一時的に落ち着かせるのが効果的です。特に糖分を含んだ軽食は、脳と胃腸の空腹信号を和らげてくれます。
◯おすすめの食品例
・果汁100%のジュース(少量)
・ビスケットやクラッカーなどの消化にやさしいスナック
※糖分や脂質が多すぎる食品はかえって腸を刺激することがあるため、摂取量は控えめにしましょう。
お腹が鳴らないようにする方法

お腹が鳴らないようにする方法として、以下の7つが挙げられます。
- 食べ物をゆっくりよく噛んで食べる
- ガスが発生しやすい食べ物は控える
- 刺激の強い食べ物は控える
- 消化を助ける食品を摂取する
- 適度に運動する
- ストレスをため込まない
- 整腸剤を活用する
それぞれ解説します。
食べ物をゆっくりよく噛んで食べる
早食いはお腹が鳴る大きな原因の一つのため、食べ物はゆっくりよく噛んで食べることが大切です。
食事をするときは1口につき20〜30回を目安に、ゆっくりよく噛んで食べましょう。
噛むことで唾液とよく混ざり、消化がスムーズになるため、腸への負担も軽減されます。
また満腹感も得やすくなり、食べ過ぎの予防にもつながります。
ガスが発生しやすい食べ物は控える
お腹が鳴らないようにするためには、ガスが発生しやすい食べ物は控えることが大切です。
ガスが発生しやすい食べ物の一例は、以下の通りです。
- 小麦製品(パンや麺類)
- 豆類
- イモ類
- 玉ねぎ
- ごぼう
- きのこ類
- リンゴ
これらの食品に含まれる糖質は小腸で分解されにくく、大腸で発酵してガスを生じるため、お腹の音を引き起こしやすくなります。
また炭酸飲料やビールなど、ガスそのものを含む飲み物もなるべく避けた方が良いでしょう。
刺激の強い食べ物は控える
唐辛子やカフェイン、アルコールなどの刺激物は、腸を過剰に刺激してぜん動運動を活発にしてしまうため、お腹が鳴る原因になります。
これらを過剰に摂取すると胃腸に負担がかかり、消化不良やガスの発生につながることもあるため注意が必要です。
また上記の刺激物だけでなく、冷たい飲み物やアイスクリームなどもぜん動運動を活発化させるため、なるべく控えた方が良いでしょう。
消化を助ける食品を摂取する
消化を助ける食品を摂取することで、お腹の音を予防できます。
消化を助ける食品としては、ヨーグルトや納豆などの発酵食品、生姜やパイナップル、パセリ、ミントなどが挙げられます。
また食物繊維を適度に摂ることで腸内の老廃物を排出しやすくし、ガスの発生を抑えることも可能です。
ただし繊維の摂りすぎは逆効果になる場合もあるため、バランスの取れた食事を心がけましょう。
適度に運動する
腸の動きを整えるためには、適度に運動することが大切です。
運動によって腸のぜん動運動が促進され、ガスや内容物がスムーズに移動しやすくなります。
これにより腸内でガスが溜まることを防ぎ、お腹の音の発生を抑えられるでしょう。
激しい運動をする必要はなく、1日20〜30分のウォーキングや軽いストレッチでも十分効果があります。
長時間座りっぱなしの生活を送っている方は、1時間ごとに立ち上がって軽く体を動かすだけでも腸に良い刺激を与えられるため、ぜひ意識してみてください。
ストレスをため込まない
お腹が鳴るのを防ぐために、ストレスをため込まないようにしましょう。
ストレスを軽減するためには、十分な睡眠や規則正しい生活リズム、そして適度なリラックスタイムを確保することなどが大切です。
また深呼吸や瞑想、ヨガなどを取り入れるのも効果的です。
好きな音楽を聴く、自然の中で過ごすなど、自分に合ったストレス発散方法を見つけ、ストレスをため込まないように心がけてみてください。
整腸剤を活用する
生活習慣や食事の改善だけではお腹の音が改善しない場合、整腸剤を活用してみるのも一つの方法です。
整腸剤には、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を補うタイプ、腸の動きを整える漢方薬、腸内ガスの発生を抑えるガス吸着剤などさまざまな種類があります。
市販薬であればドラッグストアでも購入でき、軽い不調に対しても使いやすい特徴があります。
ただし症状が慢性的に続く、痛みや体調不良を伴う場合は、自己判断せず医療機関に相談することが大切です。
まとめ
お腹が鳴るのは、消化管が食べ物やガス、液体を移動させる際の動きによるもので、自然な生理現象です。
しかし空腹だけでなくストレスや生活習慣の乱れ、腸内環境の悪化が影響している場合もあり、頻度が多かったり不快な症状を伴ったりするようであれば注意が必要です。
症状が慢性的で気になる場合は、消化器系の病気が隠れていることもあるため、医療機関での相談も検討しましょう。
えさか駅前にしごりおなかとおしりのクリニックは、お腹やお尻のさまざまなお悩みに対応しています。
内視鏡検査やCT検査、日帰り肛門手術なども行っているため、気になる症状がある方はぜひ当院までご相談ください。